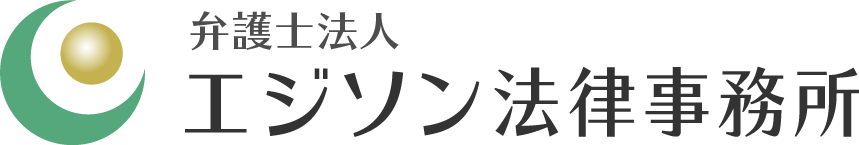コラム
賃貸マンション建て替え時の立ち退き料の相場|住居・店舗・事務所に分けて解説

大家側都合によるマンションの建て替えにあたって、そこに住む入居者はオーナーから立ち退きを求められます。
この場合、立ち退きを余儀なくされる入居者には、オーナー側から引越し費用などの名目で立退料が支払われることが通常です。
では、マンションの建て替えによる立ち退きにあたって、入居者はどの程度の立ち退き料を受け取れるのでしょうか。
また、マンションの一室を店舗として使っていた場合の立ち退き料はどうなるのでしょうか。
本記事では、マンション建て替えの際に入居者に支払われる立ち退き料の相場について、住居・店舗の2つのパターンから解説します。
立ち退き料とは
賃貸物件の賃貸人であるオーナーが賃借人である入居者に対し、オーナー都合で物件からの退去を求める時には、入居者には引越し代や迷惑料として金銭が支払われます。
これを、立ち退き料と呼びます。
立ち退き料は、引越し代や新居の契約費用、家賃差額など、退去にあたって発生する費用に迷惑料を乗せた金額で算出されます。
とはいえ、立ち退き料の支払義務が法律上定められているわけではありません。そのため、立ち退き料の法律上明確な計算方法の定めもありません。
しかし、オーナー側の一方的な賃貸借契約の解除を受け入れ、円滑に退去してもらう目的で、オーナーが入居者に立ち退き料の支払いを打診することは珍しくありません。
立ち退き料は老朽化等を理由とする建物の建て替えや解体、オーナーの自己使用、相続対策等による売却など、主に「オーナー都合」による退去要請にあたって、補償として支払われるものです。
(具体的な計算方法は、「立ち退き料の計算方法|引越し費用・家賃差額・迷惑料まで徹底解説」をご覧ください。)
借主側の賃料の滞納や騒音などの契約違反による退去や、定期借家契約の期間満了による退去など、オーナー都合ではない退去で支払われることはないのでご注意ください。
立ち退きには「正当事由」が必要
賃貸物件のオーナーは、どんな場合にでも入居者に立ち退きを求められるわけではありません。立ち退きを求めるには、「正当の事由」が必要になります。
借地借家法が定める「正当の事由」
賃貸借契約について定めた借地借家法では、賃貸人による賃貸借契約の解約について次のように定めています。
【借地借家法 第二十八条 「建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件」】
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
(e-Gov法令検索 借地借家法より)
記載のとおり、オーナーが入居者に立ち退きを求めることができるのは、「正当の事由があると認められる場合」のみなのです。
「入居者のことが気に入らないから」「もっと高い賃料を払ってくれる人を見つけたから」などという不当な理由では、立ち退きを求めることはできません。
また、「建物が老朽化しているから建て替える必要がある」という理由も、それが必ずしも本当の目的なのか、本当に建て替えなければならないほどに老朽化しているのか等を検証する必要があります。
「正当の事由」を補う「財産上の給付」
借地借家法第28条には、「財産上の給付」という言葉が記載されています。
この「財産上の給付」とは、いわゆる立ち退き料のことを指していると理解して頂いて構いません。
条文では、「財産上の給付」である立ち退き料が「正当の事由」の補完要素になることが定められています。
このことから、「正当の事由」と「財産上の給付(立ち退き料)」の間には次の関係が成り立ちます。
・「正当の事由」が強ければ、「財産上の給付(立ち退き料)」は少なくなる
・「正当の事由」が弱ければ、「財産上の給付(立ち退き料)」は多くなる
強い「正当の事由」には、オーナーによる自己使用の必要性が高いケース(他に不動産を所有しておらず、その物件を使用する喫緊の必要性に迫られているなど)が当てはまります。
老朽化等を理由とするマンションの建て直しは、今にも崩壊の危険性があるなどの緊急性の高い場合を除き、「正当の事由」としては必ずしも強いとは言い切れない場合が多く見られます。
老朽化等を理由とする退去要請にあたっては、入居者はある程度の額の立ち退き料を受け取れると考えられます。
入居者がオーナー都合による賃貸物件の退去要請に適切な対応をするには、オーナーの主張する「正当事由」の強弱にも注目することが大切です。
賃貸マンション・ビルの立ち退き料の相場
ここからは、自身が居住する賃貸マンションから立ち退きを求められた場合に受け取れる立ち退き料の相場についてみていきましょう。
住居の場合
住居として利用していた場合の賃貸マンションの立ち退き料の目安と内訳は、賃料の6か月~12か月程度と言われることが多いです。
しかし実際は物件の状況やオーナーの属性、その他個別具体的な事情に応じて判断されるべきものです。
実際に下記の実例を見ていただければ、金額にバラつきがあることが分かります。
参考までに、以下の表に記載されているような要素を勘案することも多く見られます。
【立ち退き料の内訳項目】
・引越し及び設備移転費用
・新居への引越し費用
・エアコンや通信機器などの設備移転費用
・不用品の処分費用など
・新居の契約費用
・新居の契約にかかる敷金、礼金
・仲介手数料
・保証料など
・家賃差額
・新居と旧居の家賃の差額
・迷惑料
・立ち退き協力に対する謝礼、慰謝料としての金銭
最終的には、大家との交渉を経たうえで、概括的に決められることが通常です。
底意に至るまでの間の交渉の要素としての引っ越し費用や家賃相場などは地域によって大きく異なるため、具体的な金額はやはり個別具体的な事情に応じて算出されることになります。
店舗の場合
これに対し、ビルのテナント部分を不特定多数の顧客向け店舗として利用していた場合についてみていきます。
店舗として利用していた場合の賃貸マンションの立ち退き料は、店舗の業種や営業年数、収入条項、移転先候補の有無やその場所、その他事情も加味されて判断されます。
そのため、住居の場合よりも交渉が複雑になるといえるでしょう。
店舗の立ち退きの場合、住居よりも支払われる立ち退き料は高額になる傾向にあります。
なぜなら、新店舗への移転費用だけでなく、内装・設備工事の費用や移転休業による営業損失などもその対象となるためです。
分譲マンション・ビルの区分所有(持ち家)の場合の立ち退き料
建て替えによって分譲マンションにおいて、開発業者等が退去を求めている場合には、賃貸マンションと異なり、入居者は立ち退き料ではなく、売却することを求められるため、売却交渉を行うこととなります。
なお、都市再開発法に基づく再開発の場合や、売却ではなく交換を選択する場合には、建て替え後に再入居するケースも考えられます。
立ち退き料が支払われない場合の対処法
オーナー都合でマンションからの立ち退きを求められたにも関わらず、立ち退き料の支払いに応じてもらえない場合、どうすればいいのでしょうか。
この章では「立ち退き料が支払われない場合」の対処法を2つ解説します。
立ち退き請求には応じない
大家から「裁判をする」等言われることもあるかもしれませんが、立ち退き料が支払われない、その額が十分でない、そもそも立ち退きたくという事情がある場合には、ただちに立ち退きに応じることは避けましょう。
双方の交渉が決裂すれば、裁判に発展する可能性があります。裁判では、オーナー側の述べる事情が「正当事由」に該当するかが争われます。
「正当事由」が認められれば入居者は強制的に立ち退くことになり、これが認められなければ入居者はその物件に住み続けることができます。
弁護士などの専門家に相談する
とはいえ、一度紛争になった大家の持ち物である物件を使用し続け、また直接大家からの立退き請求に対応することはストレスになるのも事実です。
また、具体的な立ち退き料の金額を交渉するにあたっては、知識と経験も必要になります。しかし一般の入居者にとって、このような紛争混じりの交渉はハードルの高いものでしょう。
その場合、弁護士などの専門家への代理交渉の依頼が、自身の希望を実現するのには適切な手段といえます。
法律の知識や経験に長けた弁護士などの専門家の手を借りれば、入居者は交渉をより有利かつスムーズに進められます。
まとめ
賃貸物件のオーナーが、物件からの立ち退きを求める入居者に対し、引越し代や迷惑料等の補償として支払う金銭を一般に立ち退き料と呼びます。
立ち退き料の支払いは、法的に定められたものではありませんので、直ちに大家との間で立ち退き料の話になるとは限りません。
しかし立ち退き料は、立ち退きの要請にあたって必要になる「正当事由」を補完する要素となるため、一定の立ち退き料が提示されることも少なくありません。
ただし、その金額としてどの程度が適切なのか、また退去の時期や方法、その他の条件など、何が適切なのかは素人判断だと難しいのが現状です。
さらに、立ち退き料については、オーナー側から支払いの意思が提示されないこともあります。
そのような場合には、ただちに大家側からの請求に対応するのではなく、弁護士に相談することを検討しましょう。
弁護士に交渉を依頼すれば、より有利な条件で問題を解決できる可能性があります。
エジソン法律事務所では、立ち退き料の増額交渉を代行しております。
「大家から提示された立ち退き料が、妥当かどうかわからない・・・。」という場合は、お気軽に無料相談をご利用ください。
エジソン法律事務所HP:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢