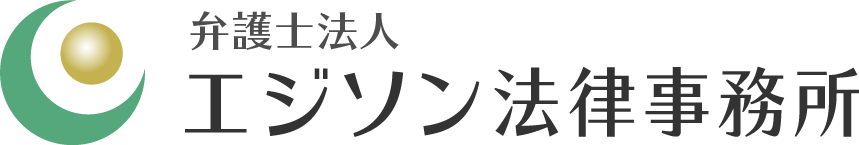コラム
賃貸借契約の更新拒絶の通知が届いた方へ:とるべき行動を弁護士が徹底解説

賃貸物件に住んでいる方は、最初に貸主である大家と賃貸借契約を交わしています。通常の賃貸借契約では契約期間満了時に更新され、入居者が解約を申し出ない限り契約は続くケースがほとんどです。
しかし賃貸借契約の期間中、稀に大家側から更新拒絶の通知を受けることがあります。
この通知を受けた場合、入居者はどう行動すれば良いのでしょうか。
今回は、賃貸借契約の更新拒絶を大家から通知された場合に取るべき行動について、わかりやすく解説します。
基本的に貸主から一方的な更新拒絶はできない
貸主は基本的に、自身の都合によって賃貸借契約の更新拒絶を行うことができません。(家賃滞納やその他賃貸借契約違反のケースを除く)
それは借地借家法が、立場が弱くなりやすい借主の権利を強く保障しているためです。
借地借家法第28条では、「貸主が賃貸借契約の更新拒絶を申し出るには『正当の事由』が必要である」という旨が記されています。
例えば、貸主が賃貸借契約を拒絶する際、下記のような事情が考えられます。
・老朽化が進んでいて倒壊の恐れがある
・補強には高額な費用が必要であるため、建て直したい
・十分な立ち退き料を支払う用意がある
一方で借主側でも、下記のような物件の使用を継続したい事情があるでしょう。
・退去が必要なほど老朽化が進行しているとは思えない
・物件が職場から近いため、生活に欠かせない住まいである
・家賃などの滞納歴もない
このような貸主・借主の事情が総合的に判断され、貸主の更新拒絶の申し出に正当性が認められるかどうかが決まります。
よって貸主側からの一方的な更新拒絶の事情だけで、貸主に正当の事由があるかどうかは判断できません。このような理由から、貸主からの一方的な更新拒絶はできないのです。
この立ち退きの正当性は、「正当事由」と呼ばれています。詳しく知りたい方は「【賃貸の借主向け】立ち退きの正当事由を弁護士が徹底解説」をご覧下さい。
賃貸借契約の更新拒絶が来たら取るべき行動
更新拒絶通知を受けた時には、通知が法的に有効であるか確認するためにも、借主は次の行動を取る必要があります。
①更新拒絶の通知の確認
②現在の賃貸借契約の確認
③立ち退きに詳しい弁護士へ相談
借主が取るべき3つの行動について、詳しくみていきましょう。
①更新拒絶の通知の確認
貸主から更新拒絶通知が来たら、まずはその内容をよく確認する必要があります。
通知には、更新拒絶の理由や事情、条件、退去日などが記されているはずです。これらの情報は、通知が法的に有効であるのか判断する証拠となります。また、その後の交渉にあたっても、条件を詰めるための重要な要素となります。
従って、受けた通知は放置したり捨てたりせず、慎重に確認してから保管しておくようにしましょう。
通知について確認すべき具体的なポイントについては、次章で詳しく解説します。
②現在の賃貸借契約の確認
貸主から更新拒絶を受けた時には、現在の賃貸借契約が普通借家契約と定期借家契約のどちらであったか、確認する必要があります。
賃貸借契約は、普通借家契約と定期借家契約に分かれます。
普通借家契約は、一般的な賃貸借契約です。普通借家契約では契約期間が満了しても、借主が解約を申し出ない限り、契約はそのまま更新するとみなされます。
一方の定期借家契約とは、契約時にあらかじめ契約期間が決まっている形式の賃貸借契約を指します。定期借家契約では契約期間満了時、再度賃貸借契約を締結しない限り、借主はその物件から退去する必要があります。
「正当の事由」の有無によって立ち退きを拒否したり立ち退き料を請求したりできるのは、普通借家契約の場合だけであることを理解しておきましょう。
③立ち退きに詳しい弁護士へ相談
通知や契約の内容を確認したら、立ち退き問題を取り扱う弁護士への相談も検討しましょう。
貸主の更新拒絶による物件からの立ち退きでは、「正当の事由」の有無の判断が非常に重要です。退去に応じる場合、立ち退き料の増額のため貸主との交渉をうまく進めなければなりません。
とはいえ、立ち退きやその交渉に慣れている借主はほとんどいません。法的な判断や交渉を自分自身で行うのは、極めて困難でしょう。
弁護士は、法律の知識と経験により、「正当の事由」を正しく判断し、交渉も代理で担うことができます。弁護士が入ることで交渉が有利に進む可能性は高くなり、場合によっては立ち退き料の増額も期待できるでしょう。
何より「借主の負担を軽減できる」のは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
立ち退き問題は一人で抱え込むのではなく、弁護士の手を借りることをおすすめします。
エジソン法律事務所では、立ち退き料の増額交渉を代行しております。
エジソン法律事務所の弁護士費用や交渉の流れについては、「エジソン法律事務所・立ち退き料交渉ホームページ」をご覧下さい。
賃貸借契約の更新拒絶で確認するべき項目
更新拒絶の通知を受けた時には、必ず次の項目について確認を行うようにしましょう。
①正当の事由
②立ち退き料
③通知日と契約満了日
上記3つの項目について、何を確認すべきか詳しくご説明します。
①正当の事由
通知を受けてまず確認しなければならないのが、更新拒絶の理由が「正当の事由」に該当するかどうかです。
「正当の事由」とは借地借家法第28条に示されているもので、その判断は次の5つの要素を鑑みて総合的に行われます。
・貸主・借主それぞれの建物使用の必要性
・建物の賃貸者についての従前の経過(契約の経緯や家賃の支払い状況、契約違反の有無、信頼関係破綻の有無など)
・建物の実際の利用状況(利用頻度や目的など)
・建物の実際の状態(老朽化の程度、修繕する場合の費用など)
・立ち退き料の支払いの有無とその金額
上記の5つの要素の中でも、最も重要なのが「1, 貸主・借主それぞれの建物使用の必要性」です。
例えば、貸主が生活に困窮していて対象物件以外の住居確保が難しい場合や、入居者の身に危険が迫るほど建物の老朽化がひどい場合などには、貸主側の建物使用の必要性が高いとして、「正当の事由」が認められる可能性があります。
そんな時に貸主側から借主側に支払われることが多いのが、「立ち退き料」です。
②立ち退き料
立ち退き料とは、更新拒絶によって対象の物件から立ち退いてもらうにあたって、補償の意味を込めて、貸主から借主に支払われる金銭のことです。
前述のとおり、立ち退き料の支払いの有無とその金額は、「正当の事由」を判断する5つ目の要素です。貸主の主張する理由や事情が「正当の事由」として弱い場合であっても、貸主が適切な金額の立ち退き料を支払えば、「正当の事由」が認められる可能性があります。
つまり、立ち退き料は「正当の事由」の補完要素であると考えると良いでしょう。
立ち退き料が「正当の事由」を補完する点については、借地借家法第28条にて示されています。この条文に示された「財産上の給付」が、立ち退き料です。
立ち退き料の適切な金額はケースによって異なります。貸主の主張が「正当の事由」として強い場合は立ち退き料の金額が低く、反対に貸主の主張が「正当の事由」として弱い場合は立ち退き料の金額が高くなるのが一般的です。
立ち退き料の具体的な計算方法は、「立ち退き料の計算方法|引越し費用・家賃差額・迷惑料まで徹底解説」にて詳しく解説しています。
③通知日と契約満了日
貸主による更新拒絶が認められる条件は、「正当の事由」だけではありません。通知のタイミングにも条件があります。
貸主による更新拒絶の通知は、契約満了日の6カ月以上前までに行わなければならない旨が、借地借家法第26条に定められています。もし賃貸借契約満了日まで6カ月を切るタイミングで貸主から通知が来ても、それは法律に違反するものであり、無効になると考えられます。
従って、貸主から通知が来た時には、その通知日と賃貸借契約の契約満了日を調べ、「通知日から契約満了日まで6カ月以上の期間が空いているか」を確認するようにしましょう。
立ち退き料の相場
立ち退き料の相場を、一概に述べることはできません。なぜなら、立ち退き料の金額は、ケースによって大きく異なるためです。
よく、立ち退き料の相場は家賃の6カ月〜1年分と言われますが、これは目安にすぎません。
実際には借主・貸主双方の事情や、地域や物件の規模、借主の居住期間など様々な事情が考慮された結果、立ち退き料が数カ月分に留まることもあれば、数年分にまで及ぶこともあります。
もし「立ち退き料の相場をざっくりでも良いから知りたい」という方がいらっしゃいましたら、弊所の過去の事例を御覧ください。
過去の立ち退き料請求の事例から、ご自身の立ち退き料の概算を求めることができます。
立ち退き料増額の実例:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
賃貸借契約の更新拒絶の通知が来た際の注意点
更新拒絶の通知が来た際に、すぐに契約解除および建物からの退去を了承するのはおすすめできません。退去に応じるにせよ応じないにせよ、まずは交渉を行い、貸主からより有利な条件を引き出すことが大切だからです。
最初から退去を了承してしまえば、貸主の提示した条件を全て受け入れることになり、借主が然るべき補償を受けられない可能性があります。
通知を受け取ったら、返答は一旦保留し、交渉に向け手続きを進めるようにしましょう。
また、更新拒絶を受け入れずに物件に居座り続けた場合や交渉がまとまらない場合などには、貸主から訴訟を起こされる可能性があることも理解しておきましょう。訴訟では、貸主借主双方の主張をもとに、借主の立ち退き請求の正当性を判断することになります。
更新拒絶の通知が届いたときには、可能な限り早めに弁護士へ相談することをオススメします。
立ち退き料の交渉は弁護士へ相談を
賃貸物件の貸主から更新拒絶の通知が届いた場合には、弁護士へ相談しましょう。弁護士は、「正当の事由」の判断や交渉、訴訟まで、関連する手続きを代理で行います。手厚いサポートを受ければ、借主も不安を軽減できるでしょう。
エジソン法律事務所では、立ち退きに関するトラブル解決のためのサポートをお引き受けしています。
実績豊富な弁護士が、より有利な条件を引き出すために代理交渉を担い、万が一の訴訟にも対応いたします。
相談料0円・着手金0円の完全成功報酬制なので、初期費用の支払いに不安がある方もお気軽にご相談ください。
エジソン法律事務所:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢