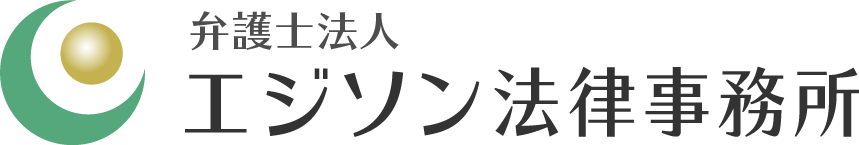コラム
【賃貸】立ち退き請求を拒否して居座ることは可能?正当の事由等について詳しく解説

賃貸物件では、稀に貸主から立ち退きを求められることがあります。
しかし、住居からの急な退去の申し出をすぐに受け入れられるものではありません。「今の部屋から出ていきたくない」「このまま住み続けたい」と考える人は、少なくないでしょう。
では、立ち退き請求を受けた借主がそれを拒否し、賃貸の部屋に居座ることは可能なのでしょうか。
今回は、立ち退きを拒否して賃貸物件に居座ることの可否と、それを決める「正当の事由」についてわかりやすく解説します。
立ち退き請求を拒否して居座ることはできるのか
貸主による立ち退き請求には「必ず従わなければならない」という訳ではありません。実際は立ち退きの請求を拒否し、居座ることができるケースもあります。
立ち退き請求を拒否できるかどうかは、貸主が主張する立ち退き理由が借地借家法上の「正当の事由」に該当するかどうかによって決まります。
貸主側に十分な「正当の事由」があると認められた場合、借主は物件から退去しなければなりません。しかし貸主側の「正当の事由」が弱く、立ち退きが認められなければ、借主は退去せず、そこに住み続けることができるのです。
ただし立ち退きの正当事由を正式に判断するのは、裁判の段階になってからです。
つまり極論を言ってしまうと「裁判を起こされ、裁判所から明け渡すよう求められない限り、居座れる」ということになります。
ただし、そうなる前に弁護士に一度ご相談いただくことをおすすめします。
借地借家法における 「正当の事由」
借地借家法は、土地や建物の賃貸借契約に関する決まりを定めた法律です。その第28条には「貸主による賃貸借契約解約の申し入れは、正当の事由がある場合のみ認められる」という内容が示されています。
「正当の事由」がなければ立ち退き請求は認められず退去する必要もないと前述したのは、この条文があるためです。
また、「正当の事由」の有無は、次の要素を鑑みて総合的に判断されます。
・貸主/借主それぞれの建物使用を必要とする事情
・賃貸借に関するこれまでの経過
・実際の建物の利用状況
・建物の現況
・立ち退き料の支払いの有無と金額
そもそも借地借家法は、立場が弱くなりやすい借主の権利保護を重視する法律です。
立ち退き請求が認められるためには、借主が納得する相当の理由が必要であり、また補償としての立ち退き料も併せて支払われるのが合理的だと考えられます。
貸主から提示される「正当の事由」とは
ここからは、賃貸借契約上の「正当の事由」に該当し得る具体的な例についてご説明します。
以下の理由を貸主が提示した場合には、「正当の事由」があるとして、立ち退き請求が認められる可能性があります。
賃貸借契約違反
物件の貸し借りを行うにあたり、貸主と借主は最初に賃貸借契約を締結しなければなりません。
この契約では物件利用にあたっての細かなルールを定めますが、借主が入居後にこのルールに違反した場合、「賃貸借契約違反」を理由に貸主が立ち退きを求めることがあります。
先ほど、立ち退きには「正当の事由」が必要だと述べました。借主による重大な賃貸借契約違反は、貸主が求める立ち退きの「正当の事由」に該当すると考えられます。
自身の重大な契約違反によって立ち退きを求められた場合、立ち退きの請求を拒否し、居座り続けることには問題があります。最悪の場合、裁判所から強制執行を受け、強制的に退去させられる可能性もあるので、注意が必要です。
建物の老朽化
「建物が老朽化している」という理由で立ち退きを求めるケースはよくあります。
しかし実際の判例を見てみると、「老朽化が進んでいる」という理由のみを正当事由として、立ち退き請求が認められることは稀です。一体なぜでしょうか。
それは明け渡しを求められる建物の多くが、軽微な老朽化にとどまっているためです。
建物の老朽化が「正当の事由」が認められるためには、
・建物の劣化がひどく入居者に危険が差し迫っている
・耐震性能が基準を満たしておらず建物が倒壊する危険性がある
といった、重度の老朽化が認められる必要があります。
また、このような重度の老朽化を理由にした立ち退きであっても、借主は貸主に、立ち退き料の支払いを求めることができる可能性もあります。
老朽化が原因の立ち退きでもらえる立ち退き料については、「【老朽化が原因の立ち退き】退去費用は出してもらえない?」にて詳しく解説しています。
立ち退き請求後に居座った判例
ここからは、貸主からの立ち退き請求を受けて貸主が退去せず、裁判に発展した事例をご紹介します。
【裁判までの流れ】
2000年8月、借主は、当時貸主と賃貸借契約を締結し、アパートを借りた。その後借主はその物件に住み続けたが、2008年の更新で「次の更新をしない」旨で合意し、2010年に契約は満了を迎えた。
しかし、借主がその物件から退去せずそのまま住み続けたことから、貸主は借主からの家賃と共益費の受け取りを拒否。結果、借主は家賃と共益費を供託し続けていた。
その後、2019年に貸主の子どもがアパートの所有権を相続し、再び賃貸借契約の解約を申し出たものの、借主は応じず、貸主は明け渡し訴訟を提起した。
【事案のポイント】
・アパートは築50年超の木造建築である
・アパートは耐震診断で倒壊の可能性があると診断されており、貸主はアパートの一部について応急措置を行なっている
・2019年からアパートには借主だけが入居しており、収益性は悪化している
・貸主は新たな建築計画を策定しており、それを実現するに十分な流動資産を保有している
・貸主は借主に家賃・共益費の6か月分である27万円、または裁判所が定めた金額の立ち退き料を支払うつもりでいる
【裁判所の判断】
老朽化・収益性悪化の状況を踏まえると、貸主が新たな建築計画によりこれらの問題を解決しようとするのは合理的であり、計画遂行のための資金面での現実性も認められる。従って、貸主が物件の明け渡しを求める必要性は相当程度高い。
一方、借主は30年以上アパートに住み続けており、70歳を超える年齢を考えても、建物使用の必要性は高い。
しかし、借主は2008年の「今回限りで更新終了」という契約に合意しているにも関わらず、それから10年以上もアパートに住み続けている。このことから、建物使用の必要性は相対的に低下していると考えられる。
これらの事情からみると、貸主の主張はただちに「正当の事由」となるものではないが、立ち退き料の支払いによってその補完は可能である。従って、貸主が借主に27万円の立ち退き料を支払い、借主はそれを受け取ってアパートを明け渡すべきである。
(参考:https://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=39/ No.1/R3.12.14/東京地裁)
このケースでは、立ち退きを言い渡されてから10年以上もの間、居座り続けていました。
この判例のように多くのケースでは、たとえオーナー都合の立ち退き請求を受けたとしても、貸主の「正当の事由」が認められない限り、居座り続けることができます。
立ち退き請求に対しては、貸主側の「正当の事由」を正しく判断した上で対応を決めることが重要です。
立ち退き請求が来たら行うべきこと
立ち退き請求を受けた時には、慌てず冷静に適切な対応を取ることが大切です。
まずは、次のご紹介する3つの行動を取り、その後の対応を検討しましょう。
①すぐに合意しない
立ち退き請求を受けて、すぐに合意するのはおすすめできません。
なぜなら、すぐに合意してしまうと条件の交渉ができず、適切な金額の立ち退き料が受け取れない、あるいは自身の希望とは異なる条件で退去しなければならなくなる可能性が高まるためです。
まずは返答を保留し、交渉による条件のすり合わせを希望するようにしましょう。
ただし、もし立ち退き請求の理由が、借主自身の家賃の不払いやその他契約違反である場合には、大家との関係回復に早急に努めることが大切です。借主の契約違反により「双方の信頼関係が破綻している」と判断される場合には、貸主による立ち退き請求が認められ、最終的に強制執行の手続きが取られることもあるためです。
もし契約違反で立ち退きを求められた場合には、貸主に対して誠意を持って対応するようにしましょう。
②通知書の確認
立ち退きにあたっては、まず貸主から立ち退き通知書が送付されます。この通知書には、立ち退きを求める理由や立ち退き料、退去期限など、立ち退きに関する条件が記されているので、内容をよく確認するようにしましょう。
その上で、立ち退き料は適正な金額か、提示された条件と自分の希望に乖離はないか把握し、交渉の方向性を決めていきます。
この判断が難しい場合には、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
また、立ち退きの通知については、賃貸借契約満了の6か月〜1年前までに行うことが、借地借家法で義務付けられています。これを守らず、「3か月以内に立ち退いてください」「来月中に退去してください」というような請求をされた場合には、応じる必要はありません。
③現在の契約内容の確認
貸主との間で締結した現在の契約内容を再確認することも重要です。契約内容によっては、立ち退き料の支払いが発生しないこともあるためです。
例えば、更新が原則の「普通借家契約」ではなく、更新をしない「定期借家契約」を締結していた場合、契約満了時には借主は必ず退去しなければなりません。この場合、契約時に満了時の退去に合意しているため、当然立ち退き料も支払われません。
他にも、立ち退きに関する決まり事が契約に盛り込まれていなかったか、契約時の書類をよく確認しておくようにしましょう。
まとめ
法律は借主の権利保護を重視するため、貸主の勝手な主張が「正当の事由」と認められるケースは比較的少ないです。この場合、借主は立ち退き請求に応じず、物件に住み続けることができます。
また、その物件に住み続けることにこだわりがない場合には、トラブルを避けるためにも、立ち退き料をしっかり受け取って立ち退き請求に応じるというのも、一つの選択肢でしょう。
この記事を執筆しているエジソン法律事務所は、立ち退き料の増額依頼を承っています。
もし借りている住宅や土地から立ち退きを求められたら、エジソン法律事務所への相談をご検討ください。当事務所では、実績豊富な弁護士が交渉や裁判を担当し、完全成功報酬制で立ち退き料を増額できるよう尽力いたします。
貸主の主張の「正当の事由」への該当性を正しく判断し、立ち退き拒否の可否についてアドバイスすることも可能です。今の住居から立ち退きたくないという方も、安心してご相談ください。
エジソン法律事務所・立ち退き料増額ホームページ:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢