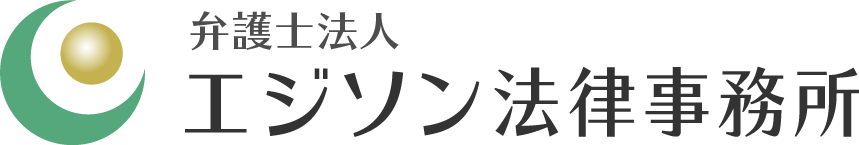コラム
立ち退きの裁判の流れは?通知・交渉・裁判・判決まで徹底解説

アパートやマンションといった賃貸からの立ち退きでは、立ち退きを求める賃貸人とそれに応じたくない賃借人の間で、裁判を行う場合があります。
交渉での合意、または裁判での和解ができない場合には、賃貸人・賃借人は裁判所の判決を待ち、それに従うことになります。
では、立ち退きではどのような流れで裁判までの手続きが進められていくのでしょうか。また、裁判の結審までにはどれくらいの期間を要するのでしょうか。
今回は、立ち退き問題の裁判までの流れをわかりやすく解説します。
1.立ち退きの通知
立ち退きにあたっては、まず物件の賃貸人または管理会社から、立ち退きを求める内容の書面が送付されます。これが立ち退き通知と呼ばれるものです。
この時送付される書面には、立ち退きを求める理由や条件、退去期日などが記載されます。書面の内容は後の交渉や裁判でも重要になるため、しっかり確認し、書面自体も保管しておくようにしましょう。
ただし、借地借家法では、「立ち退き(更新拒絶)の通知は、契約満了の1年〜6か月前までに行われなければならない」旨が定められています。従って、賃貸借契約満了まで6か月未満のタイミングで送付された通知に関しては、法律に違反するものとして、賃借人は立ち退きに応じる必要はありません。
突然賃貸人から退去を求める通知が来て、「早く引っ越さなければ」と慌ててしまう方は多いでしょう。しかし、「来月中に退去してほしい」「3か月以内に立ち退いてほしい」などといった条件(契約満了の1年〜6か月前までの通知)を満たさない無理な要求については、賃借人は受け入れる必要はないのです。
立ち退きは拒否できるのか
賃貸人や管理会社から求められた立ち退きは、必ずしも受け入れなければならないとは限りません。その立ち退きに「正当の事由」が認められない場合、賃借人は求めを拒否することができます。
「正当の事由」とは、借地借家法で定められた立ち退き要請を認めるための要件のことを指します。「正当の事由」の有無は、賃貸人・賃借人それぞれの事情や物件使用の必要性、実際の使用状況、これまでの経緯、立ち退き料の金額などを総合的に見て判断されます。
借地借家法は、立場が弱くなりやすい賃借人の権利を重視しています。賃借人の勝手な都合だけを見て「正当の事由」が認められることは基本的にありません。
例えば、複数の物件を有する賃貸人が「その物件を使いたいから」という理由だけで賃借人に退去を求めても、その立ち退きの「正当の事由」が認められる可能性は低いです。
一方、住んでいる人に危険が迫っているほどの建物の老朽化を理由に立ち退きを求め、さらに立ち退き料も支払うとした場合には、「正当の事由」が認められる可能性は高くなります。
2.立ち退き料の交渉
通知を受け取った後、賃貸人と賃借人の間で交渉が行われます。
この交渉では、立ち退きにあたっての条件を話し合うことになります。具体的には、立ち退き料の金額や支払いのタイミング、退去日、原状回復義務の扱いなどについてすり合わせます。
特に立ち退き料の金額については、慎重な議論が必要です。
立ち退き料は、急な退去の申し入れに対する補償の意味を含んでいます。十分な補償を受けるためにも、賃借人は適切な金額の立ち退き料を賃貸人に求める必要があります。
まずは提示された立ち退き料ですぐに合意するのではなく、一旦判断を保留しましょう。その後落ち着いて、借人自らが適切だと考えられる金額を提示するようにしましょう。具体的には下記のような項目が、立ち退き料算出の上で考慮されることがあります。
・転居費用
・新居契約費用
・新旧家賃差額(数ヶ月〜数年分)
・その他補償(迷惑料)
立ち退き料の具体的な計算方法に関しては、「立ち退き料の計算方法|引越し費用・家賃差額・迷惑料まで徹底解説」にて詳しく解説しています。
個別のケースによって上記の項目は変化しますが、「なぜその金額になったのか」という根拠を示せるようにしておくと、希望する金額で合意できる可能性は高くなります。
(オーナーの方は「立ち退き交渉の流れから、代行利用のメリットデメリットまで徹底解説」をご覧ください。)
合意する場合
話し合い後、受け取る立ち退き料の金額や退去日などに双方が納得できた場合には、交渉は合意へと進みます。この時合意書を作成し、合意した内容を全て書面で残すようにしましょう。
合意書は法的効力を持つ為、出来上がった書面は賃借人側でもきちんと確認することが大切です。
書面をよく確認せず、納得していない内容が記載されていたことに気づけないままサインしてしまった場合、賃借人は不利な条件を強いられる可能性があります。
書類の確認に自信がないという方は、交渉とともに、諸々の手続きを弁護士に代理してもらうのも一つの方法でしょう。
合意しない場合
交渉は、必ず合意に至るとは限りません。中には、「賃貸人が立ち退き料の請求に応じない」「条件に納得できないので退去したくない」などといった理由で交渉が決裂することもあるでしょう。
このような場合、賃貸人が訴訟を起こすかどうかによって対応は変わります。賃貸人が明け渡し請求訴訟を起こした場合には、裁判に移行します。一方で、賃貸人が立ち退き要請を諦めたり、裁判で勝てる見込みが低いと判断し訴訟を起こさなかったりした場合には、この問題はここで一旦終了となります。
3.立ち退きの裁判
明け渡し訴訟が提起された場合、裁判で立ち退きとその条件について争います。
弊所の立ち退き料請求依頼の中では、全体の約1割が裁判に至ります。
多くの場合、裁判で重要な争点となるのは、「正当の事由」の有無です。裁判官は、立ち退き要請の理由やそれぞれの事情などからそれを判断し、和解・判決へと手続きを進めます。
また、裁判は第三者の視点から結論が出される点がメリットですが、一方で終了までに長い期間を要するというデメリットもあります。
裁判の実施は1か月に1回ほど。賃貸人と賃借人が交互に主張を行っていく形なので、一般的には1年〜1年半、早くても終了までに数か月〜半年はかかるでしょう。
エジソン法律事務所では弁護士が依頼者の代理をするため、裁判に移行した場合でも依頼者が出廷する必要はありません。また、裁判に移行した場合でも追加の費用は発生しません。
和解する場合
裁判では、まず原告・被告の主張や証拠の提出が行われます。
裁判所はそれを受け、「正当の事由」の有無を判断し、和解に向けた調整を行います。
この時改めて提示された立ち退き条件に双方が納得できれば、裁判は和解で決着します。
裁判はもちろん、立ち退き問題もこれで終了し、決められた条件のもと、賃借人は物件から退去することになります。
和解しない場合
通常、裁判では判決前に、和解に向けた協議が行われます。しかし、全てのケースで和解が成立するわけではありません。「和解の余地はない!」と、片方が裁判所の判決を求めた場合、和解は成立せず、手続きは判決へと進むことになります。
この場合、裁判はさらに続きます。賃貸人・賃借人双方について、当事者尋問や証人尋問が行われ、その後に裁判所の判決が行われます。
もし裁判を通して賃貸人が主張する「正当の事由」が認められた時には、裁判所は賃貸人に立ち退き料の支払いを、賃借人に物件の明け渡しを命じることになるでしょう。
一方、「正当の事由」が認められなかった場合には、原告である賃貸人の請求は棄却され、賃借人が立ち退く必要はなくなります。
ただしエジソン法律事務所では、裁判になっても依頼者が出廷する必要はありません。弁護士が代理で対応致します。
立ち退きの裁判例
最後に、実際に起こった立ち退きに関する裁判の事例をご紹介します。
今回ご紹介するのは、立ち退き料の支払いによって「正当の事由」を補完することで立ち退き要請が認められた例です。
【立ち退きまでの流れ】
賃貸人は、自身の保有するアパートの一室について、2007年に賃借人と賃貸借契約を締結した。2009年の契約更新時に借主の意思により、本契約は期間の定めのないものとなった。
その後、2017年に貸主が死亡し、貸主の子が新たな賃貸人となった。
当時アパートは築約45年で、老朽化による倒壊の危険があることから、貸主はアパートの取り壊しを理由に、借主に対し6か月後の賃貸借契約の解約を申し入れた。
しかし、借主はこれに応じず、期日を過ぎてもアパートから退去しなかった。これを受け、貸主は明け渡し訴訟を東京地裁に提起した。
【貸主の主張】
・対象のアパートは1971年に建設されたもので、老朽化が進んでいる
・アパートの修繕・耐震工事には、あわせて3,500万円以上の費用が必要であり、賃貸人がこれを負担することは厳しい
・元貸主から業務を引き継いだため不慣れであり、今後の生活資金を確保するため、建物を取り壊して土地を売るなどして、現金を確保する必要がある
・貸主は借主に対し、立ち退き料として100万円(または裁判所が相当と認める金額)を支払う
【借主の主張】
アパートの老朽化は賃貸人の怠慢によるものである
立ち退き料は350万円が適当であり、最低でも200万円は支払われるべきだ
【裁判所の判断】
裁判所は、対象のアパートは築45年以上と老朽化が顕著であり、倒壊の可能性も高く、費用面からも取り壊しの必要性は高いことから、「正当の事由」は相当程度認められると判断した。
しかしその一方で、借主はアパートを住居としており、家賃滞納もないことから、建物使用の一定の必要性は認められるとした。
その結果、借主に立ち退き料を支払い「正当の事由」を補完することで、貸主の立ち退き要請は認められると判決を下し、貸主に 借主への100万円の立ち退き料の支払いを、借主にアパートの明け渡しを命じた。
(参考:https://www.retio.or.jp/info/pdf/124/124-178.pdf)
まとめ
賃貸物件からの立ち退きでは、通知・交渉・裁判という流れで手続きが進みます。
これら全ての工程において重要になるのが、法律の知識や交渉力。これらは、賃借人が立ち退きにあたって十分な補償を受けるために、また納得のいく条件で合意するために、非常に重要です。
とはいえ、一般の方で立ち退きに関する法的知識や交渉経験を持つ方は、ほとんどいないでしょう。
そこで検討すべきなのが、弁護士への相談です。弁護士は、立ち退きに関する手続きや交渉を代理で行なうことが可能です。立ち退き問題の実績を持つ弁護士が代理交渉を担えば、大家と話し合う必要もなく、賃借人にとってより有利な条件で合意できる可能性は高くなるでしょう。
また、手続き裁判に進んだ場合でも、手厚いサポートにより負担を軽減することができます。
エジソン法律事務所では、立ち退き料増額の依頼を受け付けています。実績豊富な弁護士が交渉を担当し、立ち退き料の増額を目指します。
当事務所は、完全成功報酬型で相談料・初期費用は0円、裁判にも対応します。まずはお気軽に相談下さい。
エジソン法律事務所・立ち退き料増額ホームページ:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢