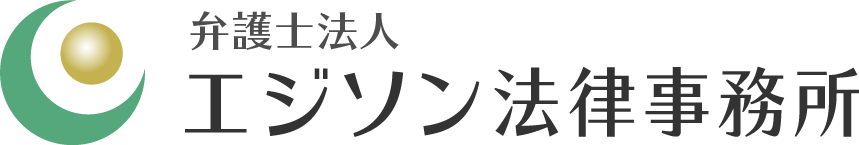コラム
こんな立ち退き料の請求禁止特約は無効になる:弁護士が詳しく解説

貸主が立ち退きを申し出るにあたって、退去を求められた入居者に対し支払う金銭を「立ち退き料」と呼びます。立ち退き料の支払いに法的義務はないものの、建物から退去してもらうことへの補償と立ち退きのスムーズな進行という観点から、賃貸人は入居者に立ち退き料を支払うことが多いです。
しかし、中には賃貸借契約時の契約内容に「立ち退き料の請求禁止特約」を入れておき、立ち退き時の立ち退き料の支払いを避けようとする賃貸人も存在します。
では、立ち退き料の請求禁止特約は、法的に有効なのでしょうか。
今回は、立ち退きにおける立ち退き料の請求禁止特約の概要と有効性について、わかりやすく解説していきます。
立ち退き料の請求禁止特約とは
「立ち退き料の請求禁止特約」とは、「賃貸人都合で立ち退きを求めた場合でも、賃借人は立ち退き料を請求することはできず、速やかに退去に応じる必要がある」旨を定めた特約のことです。
賃貸物件の入居時には、賃貸人と入居者は賃貸借契約を締結します。この時、賃貸借契約書には、立ち退き料の請求禁止特約が規定されている可能性があります。
賃貸借契約について定めた借地借家法は、立場が弱くなりやすい賃借人(入居者)の権利保護に重きを置いた法律です。
借地借家法があるため、賃貸人側から一方的に賃貸借契約を解約することは基本的にできません。賃貸人都合により契約を解約して入居者に物件から立ち退いてもらうためには、「正当事由」の提示に加え、一定の金額の立ち退き料の支払いが必要であるケースが多いです。
しかし、賃貸人にとっては、立ち退き料の支払いは負担になります。
そこで契約に盛り込まれるようになったのが、立ち退き料の請求禁止特約。
将来的に入居者に立ち退いてもらう必要が生じた場合に備え、立ち退き料の支払いを避けるために、賃貸借契約に立ち退き料の請求禁止特約をあらかじめ入れておく賃貸人が現れるようになったのです。
立ち退き料請求禁止の特約が書かれる理由
前述のとおり、立ち退き料の請求禁止特約は、「賃貸人都合での立ち退きでも入居者は立ち退き料を請求できない」旨を示す特約です。
しかし、立ち退き料の請求禁止特約を賃貸借契約書に盛り込んでいても、実際の立ち退き時には、この特約は無効とされる可能性が高いです(その理由については次章でご説明します)。
それにも関わらず、なぜ立ち退き料の請求禁止特約を契約に入れる賃貸人がいるのでしょうか。
その理由のひとつとして、貸主が立ち退き料の支払いを抑えたいと考えていることが挙げられます。
仮にこの特約が契約書に記載されていると、一部の借主は「立ち退き料は請求できない」と誤解し、そのまま退去してしまう可能性があります。
当然、特約が無効であることを理解している借主には、必要に応じて支払う必要があるでしょう。しかし中には請求せずに退去する人もいるため、結果として賃貸人にとっては経済的なメリットが生じるのです。
借主に不利な特約は無効になる
建物や土地の賃貸借契約について定めている借地借家法には、以下の条文があります。
【借地借家法第30条 強行規定】
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
(引用:e-Gov法令検索「借地借家法」)
上記条文の「この節」には「第28条 建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件」も含まれています。
つまり貸主都合の立ち退きでは、借主にとって不利な内容の特約は無効となる旨を示しているのです。
もし「立ち退き料は支払われない」「立ち退き時の敷金は借主が支払う」など、借主にとって不利な特約のある賃貸借契約を締結してしまっているとしても、その特約の効力は認められない可能性が高いです。
ただ借地借家法では「賃借人に不利なもの」に該当する特約の内容を、具体的に示しているわけではありません。そのため「賃借人に不利なもの」の基準が重要になるわけですが、これについて過去の判例では、裁判所は「それぞれの事情を考慮して総合的に判断すべきである」としています。
つまり、明確な判断基準はなく、「賃借人に不利なもの」への該当性については、個々の事例ごとに判断していくしかないのです。
とはいえ、立ち退き料は賃貸人都合で退去させられる入居者の負担を補償するためのもの。この支払いを行わないというのは、十分に「入居者にとって不利なもの」と言えるでしょう。
そう考えると、ケースバイケースではありますが、「立ち退き料の請求禁止特約」が無効になる可能性は高いと考えられます。
無効になる立ち退き料請求禁止特約の例
「立ち退き料の請求禁止特約」は多くの場合無効になります。ただし個々の事例ごとに判断するものであり、明確な判断基準はありません。
しかし、以下2つのような特約については、ほとんどのケースで無効となります。
・契約満了まで6カ月を切っていても、賃貸人による更新拒絶を通知できるとする特約
・「正当事由」なしに賃貸人の都合で立ち退き要請ができるとする特約
借地借家法第26条には、「賃貸人による更新拒絶の通知は、契約満了の1年前から6カ月前までに行わなければならない」旨が示されています。
「解約申入れを行った日から明渡しまでの期間が6ヶ月を切っていても、解約の申入れが可能」という旨の特約は、この第26条に反するため、同法30条により無効と解されます。
また借地借家法第28条には、「賃貸人による賃貸借契約の解約申し入れは、正当の事由があると認められる場合でなければ行えない」旨も示されています。
よって「正当事由の有無にかかわらず解約を申し入れることができる」のような旨の特約に関しても、同法第30条により無効になると解されます。
実際の裁判でも、「賃貸人は契約満了まで1カ月程度前に通知を行った場合でも、契約を解除できる」とする特約や「賃貸人による更新拒絶を入居者は無条件で認める」とする特約は、無効であると判断されています。
また、「賃貸人の求めによる賃貸借契約満了後に建物の明渡しに応じない場合には違約金が発生する」という特約に対し、無効と判断した判例も存在します。
なぜなら、違約金を設定することは、賃借人に有無を言わさず立ち退かせることに繋がり、正当の事由の判断が不必要になりかねないためです。
【例外】有効となった立ち退き料の請求禁止特約
無効となった「立ち退き料の請求禁止特約」がある一方で、有効性が認められた特約も存在します。
ここでは、有効性が認められる立ち退き料の請求禁止特約について、2つのケースをご紹介します。
家賃を滞納したケース
「家賃を一定期間滞納した場合には、賃貸借契約は解除となり、立ち退き料は支払われない」という内容の「立ち退き料の請求禁止特約」は、実際の判例を見ても、その有効性を認められる可能性が高いです。「家賃滞納から3ヶ月経過した場合、直ちに賃貸借契約を解除できる」という旨の特約が有効であると解された裁判例は、実際に存在します。
家賃の支払いは賃借人の負う義務であり、これを怠ったことにより賃貸借契約が解除されること、また契約解除に伴い立ち退き料の支払いは受けられないことは、当然といえば当然でしょう。
定期借家契約を結んでいるケース
定期借家契約を結んでいる場合、「立ち退き料の請求禁止特約」の有効性は認められると考えられます。
そもそも「定期借家契約」とは、あらかじめ期間が決められている賃貸借契約のこと。
借地借家法第38条では、「事前に賃貸期間を決める定期借家契約の場合、契約の更新がないこととする旨を定めることができる」とされています。
期間満了となっても契約が更新されていく「普通借家契約」と異なり、定期借家契約では契約の更新は基本的にされません。そのため、賃貸人と賃借人が再契約する場合を除き、契約満了時には賃借人は物件から出ていく必要があります。この時、立ち退き料は支払われないので注意しましょう。
ただし定期借家契約の締結時には、賃貸人は「契約が更新されない」という旨を賃借人に説明し、書面で契約を交わす必要があります。これが行われない場合、契約を更新しない旨が認められなくなる可能性があります。
立ち退きを目的とし、定期借家契約に切り替えようとする大家は多いです。詳しくは「建物の老朽化により定期借家契約に切り替えられた!?拒否する方法や正当事由について徹底解説」にて解説しています。
まとめ
「賃貸人から急に契約更新拒絶の通知が送られてきた」「立ち退き要請にどう対応すれば良いのかわからない」というような場合には、不動産トラブルを扱う弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士が賃借人との立ち退き交渉を担うことで、交渉がスムーズに、そして賃借人にとってより有利に進む可能性は高くなります。立ち退き交渉の実績豊富な弁護士であれば、過去の判例から正当事由を正しく判断し、適切な金額の立ち退き料を請求することが可能です。
エジソン法律事務所では、立ち退き料請求に関するご依頼を受け付けています。不動産問題に重点的に取り組む弁護士が、立ち退きを求められた方々が適切な補償を受けられるよう対応いたします。
弊所では相談料0円・着手金0円の完全成功報酬制を採用。万が一立ち退き料の支払いがなかった場合には成功報酬は発生しないので、費用面でも安心してご依頼いただけます。
立ち退き問題にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
エジソン法律事務所・立ち退き料増額ホームページ:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢