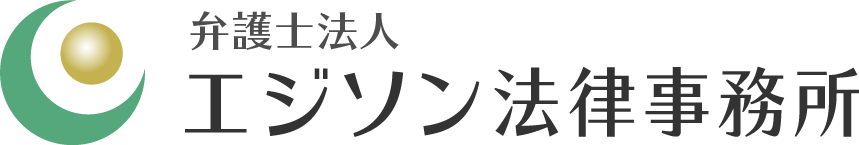コラム
【道路拡張】賃貸店舗の立ち退き料の「相場」営業補償などの算定項目を解説

公共事業では、既存道路の拡張工事が行われることがあります。
この道路拡張にあたっては、拡張予定地にある土地や建物の確保のため、国や自治体による立ち退き要請が行われることも少なくありません。
では、道路拡張を理由に立ち退きを求められた場合、そこで店舗を借りていた賃借人はどの程度の立ち退き料を受けることができるのでしょうか。
今回は、道路拡張に伴う賃貸店舗からの立ち退きについて、賃借人が受け取れる立ち退き料の相場やその内訳をわかりやすく解説していきます。
道路拡張による店舗の立ち退き料の「相場」
道路拡張のような公共用地を収容するための国・自治体による立ち退き要請では、要請の対象となった店舗や人に対し、一定の補償が行われます。それが、立ち退き料と呼ばれるものです。
公共事業に伴い、店舗オーナーが所有する店舗から立ち退く場合、立ち退き料はその土地の公示価格や基準地価に、失う面積を乗じて算出されることが一般的です。また営業状況や慰謝料なども勘案されます。
一方、賃貸の店舗から立ち退く場合には、店舗の移転費用や移転に伴う営業損失などから、立ち退き料が算出されます。
ここで例として、賃貸店舗の居酒屋が道路拡張により立ち退く場合を考えてみましょう。
条件は以下のとおりとします。※各費用の金額は仮定です。
旧店舗の家賃:20万円
新店舗の家賃:25万円
従業員数:3人
1ヶ月の収益:15万円
上記条件の居酒屋における立ち退き料の内訳と総額は以下のようになります。
【移転費用】
引っ越し費用:100万円
新店舗契約費:250万円
【家賃の差額(補償期間2年とする)】
120万円(5万円×24カ月分)
【営業補償(休業期間6カ月とする)】
従業員への休業手当(20万円×3人×6カ月):360万円
休業期間中の収益減:90万円(15万円×6カ月)
あくまで仮定ですが、ここまでの費用項目で立ち退き料の総額は920万円となります。
このように、店舗からの立ち退きにあたっては、店舗の収益や休業期間、業種業態なども勘案されます。
ケースによって立ち退き料の具体的な金額は大きく異なるため、立ち退き料の明確な相場はないといえるでしょう。
店舗に支払われる立ち退き料の種類
道路拡張によって立ち退きを求められた店舗(賃貸・所有)の賃借人および所有者に支払われる立ち退き料は、以下の項目に分類されるものが多いです。
①移転費用
②家賃の差額(賃貸の場合)
③建て直し等にかかる費用(建物の所有者である場合)
④その他の雑費
⑤営業補償
各項目について詳しく解説していきます。
①移転費用
立ち退きに伴う店舗の移転では、移転費用が補償されることが多いです。
都市開発を管轄する国土交通省では、道路拡張をはじめとした公共用地を取得するための立ち退き要請について、『公共用地の取得に伴う損失補償基準』の中で詳細を定めています。
この損失補償基準においては、「土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償」として、第31条に「動産移転料」が明記されています。その内容を要約してみましょう。
公共用地の取得により移転する動産については、通常妥当であると認められる移転先に妥当であると認められる移転方法で移転するのに必要な費用を補償する
(参考:国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準 第31条 動産移転料』)
つまり、道路拡張によって立ち退きを求められた店舗は、店舗の移転費用について、妥当な範囲内で補償を受けることができるのです。これは、所有物件からの移転であろうと賃貸物件からの移転であろうと違いはありません。
また、具体的な移転費用としては、引っ越し費用や新店舗の契約費などが該当します。
②家賃の差額(賃貸の場合)
賃貸人から物件を借りて店舗を経営していた場合の立ち退きでは、旧店舗と新店舗の家賃差額についても補償の対象となります。
国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準』では、「借家人に対する補償」として、第34条2に以下の旨が示されています。
立ち退きに伴い、賃借人が新たな賃貸物件へ移転するときに、これまで賃借していた建物の家賃が新たに借りる家賃よりも低い場合には、事情を総合的に考慮した上で、適切な補償を行う
(参考:国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準 第34条2 借家人に対する補償』)
この基準は、立ち退きにおける新旧の家賃の差額を補償する根拠となっています。
また、家賃差額が何カ月分補償されるのかは、事情を総合的に考慮して決めることになり、この点は立ち退き交渉における重要なポイントとなります。
③建て直し等にかかる費用(建物の所有者である場合)
店舗の建物を賃貸ではなく所有していた場合には、建物の移動や建て直しにかかる費用も立ち退き料の中に含まれます。
このことは、国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準』の第28条に「建物等の移転料」として定められています。
また、地方自治体が『公共用地取得の流れ』として公表している資料では、建物の移転方法として、既存の建物を移築する「家工法」と建物の建て直しを行う「機外再築工法」を挙げています。建物を移築できない場合には、再築工法、つまり建て直しの補償が行われることになっています。
建物の建て直しにおいては、実際に建て直しにかかった金額ではなく、既存の建物の経過年数などを考慮した金額が補償されます。
④その他の雑費
道路拡張に伴う店舗からの立ち退きでは、以下のような移転によって生じる雑費も補償の対象です。
・移転先または代替地等の選定に要する費用
・法令上の手続に要する費用
・転居通知費
・移転旅費
・その他の雑費
・就業できないことによる損失(営業補償として規定する一部を除く)
上記の費用が立ち退き料内の補償対象となることも、国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準』の第37条で定められています。
⑤営業補償
道路拡張による立ち退きで店舗の移転が必要になった場合、店舗のオーナーは移転期間中に店を営業することができません。これにより生じる営業損失は、大きなものになるでしょう。
公共用地取得に伴う立ち退きでは、営業補償として、移転期間中の営業損失や固定費なども補償されます。
その根拠は国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準』の第44条です。この条項では、「営業休止の補償」として、従業員への休業手当や収益減に対する補償を行う旨が示されています。
営業補償の詳しい内容については、次章で確認していきましょう。
また国土交通省の見解では、これらの営業補償は2年分の範囲内で適切な額が支払われます。ただし円滑な転業が特に困難であると認められる場合、2年以上に設定されることもあります。
店舗に支払われる営業補償の種類
ここからは、道路拡張に伴う立ち退きによって、店舗を休業しなければならない場合に支払われる営業補償の内容について解説していきます。
この場合に営業補償として補償される項目には、次のようなものがあります。
①従業員への休業手当
②休業期間中の法人税、所得税、住民税など
③休業期間中の収益減
④常連客がいなくなることへの補償
⑤経営効率悪化に対する補償
⑥その他店舗移転に伴う費用
各項目について詳しくご説明します。
①従業員への休業手当
国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準』の第44条一項では、次の旨が記載されています。
公共用地の取得に伴う立ち退きで、店舗の通常営業を一時休止する必要があると認められた場合には、通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費および従業員に対する休業手当相当額を補償するものとする
(参考:国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準 第44条一項 営業休止等の補償』)
この条項からは、休業中に従業員に対し支払う休業補償が、国や自治体側から補償されることがわかります。したがって立ち退きによる補償総額は、従業員数によっても変わるといえるでしょう。
②休業期間中の法人税、所得税、住民税など
前述した国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準』の第44条一項では、「通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費」も補償する旨が示されています。
ここでいう公租公課とは、国や自治体に納付しなければならない税金のことです。道路拡張による休業期間中は、法人税や所得税、住民税などの「公租」や健康保険料や社会保険料などの「公課」を、国や自治体に補償してもらうことができます。
③休業期間中の収益減
国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準』の第44条二項では、次の旨が記載されています。
公共用地の取得に伴う立ち退きで、店舗の通常営業を一時休止する必要があると認められた場合には、通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては所得減)を補償するものとする
(参考:国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準 第44条二項 営業休止等の補償』)
この条項では、立ち退きに伴う店舗休業中の収益(所得)の減少が立ち退き料内の補償対象となる旨が示されています。したがって、休業によって店舗の収益がゼロになったとしても、その損失は過去の収益をもとに算出した金額で補償されます。
④常連客がいなくなることへの補償
国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準』の第44条三項では、次の旨が記載されています。
休業することにより、又は店舗等の位置を変更することにより、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額を補償するものとする
(参考:国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準 第44条三項 営業休止等の補償』)
ここでいう「得意」とは、いわゆる常連客のことです。休業・移転にあたって常連客が離れてしまうリスクは、店舗にとって大きなものです。公共用地取得による立ち退きでは、「常連客が離れることによって生まれる損失」も補償の対象となります。
⑤経営効率悪化に対する補償
立ち退きにあたっては、店舗を移転したことで、経営効率がそれまでより悪化するリスクもあります。道路拡張など公共用地の取得における立ち退きでは、この「経営効率悪化」に対する補償を行うことも規定されています。
公共用地の取得に伴う立ち退きによって、通常営業の規模を縮小しなければならないと認められ、それに伴い経営効率が低下すると客観的に認められるときには、これにより生じる損失額を補償するものとする
(参考:国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準 第45条 営業規模縮小の補償』)
この条項を根拠に、経営効率低下により発生すると思われる損失も、国や自治体に補償してもらうことができます。
⑥その他店舗移転に伴う費用
公共用地取得に伴う立ち退きでは、「その他店舗移転に伴う費用」も補償されると決められています。国土交通省『公共用地の取得に伴う損失補償基準 第44条四項』では、以下のような費用が補償対象になる旨が示されています。
・店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損
・移転広告費
・その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額
移転に伴う商品の原材料の損失や、移転開店の旨を知らせる広告費などは補償対象となるため、店舗のオーナーがその損失を負担する必要はありません。
立ち退き料増額のアドバイスは弁護士へ
ここまで、道路拡張による賃貸店舗からの立ち退きで補償される立ち退き料について解説してきました。
公共用地取得に伴う立ち退きでは、今回紹介した立ち退き料の種類以外にも、例えば移転先の店内装飾の費用や仮住居が必要になった場合の費用などについて請求できる可能性があります。
立ち退きを求められる人は、少なからず精神的・体力的な負担を負うことになります。それを踏まえても、受け取れる立ち退き料はすべて請求すべきです。正しい知識を持って、立ち退き料の増額を目指しましょう。
また、立ち退き料を増額したいという場合は、弁護士へアドバイスを求めるのも手です。弁護士の手厚いサポートを受けることで、交渉や手続きはより有利かつスムーズに進む可能性があります。
エジソン法律事務所では、相談料・着手金0円で立ち退き料増額交渉の依頼を承っております。立ち退き問題にお悩みの方は、ぜひご相談ください。
エジソン法律事務所・立ち退き料増額ホームページ:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢