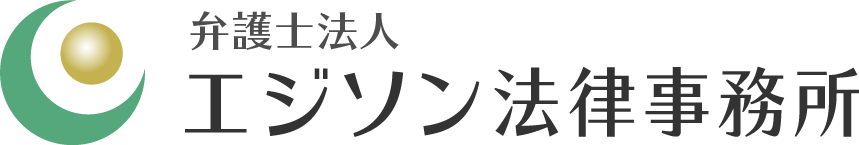コラム
立ち退き料はいくらもらえるのか?増額交渉のポイント等を解説

大家都合での立ち退きでは、多くのケースで、大家から入居者(またはテナント)へ金銭の支払いが行われます。この金銭は立ち退き料と呼ばれ、立ち退きの正当性を補完したり、入居者の損失を補償したりする役割を持つものです。
では、入居者が受け取れる立ち退き料はどれくらいの金額なのでしょうか。また、この金額を増額させるためには、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。
今回は、立ち退き料はいくらもらえるのか、また増額交渉のポイントについて詳しく解説します。
立ち退き料とは
立ち退き料は、大家都合で立ち退く入居者へ補償を行うために、大家側から支払われる金銭のことです。
立ち退き料の支払いは法的に定められたものではありませんが、その存在は建物や土地の賃貸借契約について定めた借地借家法と深い関係を持っています。
「正当の事由」とは大家による物件使用の高い必要性のこと
借地借家法第28条には、次のことが定められています。
「賃貸人(貸主)による賃貸借の解約の申入れは、正当の事由があると認められる場合でなければ行うことができない」
ここでいう「賃貸借の解約の申入れ」とは、立ち退き要請のことです。つまり、法律では「正当の事由」なしに大家が立ち退きを求めることを禁止しているのです。
では、この「正当の事由」とは何なのでしょうか。
「正当の事由」とは、対象の物件を大家が使用する極めて高い必要性・正当性のことです。それが賃借人(借主)である入居者による物件使用の必要性・正当性を上回る場合、「正当の事由」が認められます。
反対に、大家が物件を使用する必要性・正当性が低いと考えられる場合には、立ち退き要請は認められません。
この決まりは、大家が身勝手な理由で入居者を立ち退かせることを防ぐために、重要な役割を果たしています。
立ち退き料は「正当の事由」の補完要素
「正当の事由」と立ち退き料には深い関係性があります。
借地借家法第28条には、次のことも記されています。
「財産上の給付は、正当の事由の考慮要素となる」
「財産上の給付」とは立ち退き料の支払いのことを指します。この条文は、立ち退き料の支払いによって「正当の事由」は補完できるとも言い換えられるでしょう。
つまり、立ち退き理由の必要性・正当性が弱い場合には、入居者に対し立ち退き料を支払えば、大家はその必要性・正当性を補完して「正当の事由」を成立させることが可能になるのです。
大家の主張する一般的な立ち退き理由の多くは、それだけで「正当の事由」とは認められることはあまりありません。よって、正当性を補完するための立ち退き料が、多くの事例において支払われています。
立ち退き料はいくらもらえるのか
入居者にとって最も気になるのが、立ち退き料の金額ではないでしょうか。
実は、立ち退き料には法的な定めがないため、計算方法も決められていません。「正当の事由」を補完する役割を考えても、立ち退き理由やその状況によって、金額は変わって然るべきです。まさに、ケースバイケースだと言えるでしょう。
強いて「相場」を挙げるなら、その額は以下のようになります。
住居使用の物件の場合:家賃の6〜12ヶ月分程度
店舗使用の物件の場合:家賃の2〜3年分程度
上記はあくまで目安ですが、住居使用の場合に比べ店舗使用の物件からの立ち退きは、立ち退き料が高額になるのが一般的です。なぜなら、店舗の移転には多額の金銭が必要であり、また移転に伴う営業損失も発生すると考えられるからです。
ただし、弊所の立ち退き料増額の例でも紹介しておりますが、
・賃料5万円のアパートからの立ち退きで「立ち退き料120万+フリーレント3ヶ月分」
・賃料10万円のマンションからの立ち退きで「立ち退き料200万円」
など、「相場」から大きくかけ離れるケースもあります。
担当弁護士の経験によっても大きく変動するため、やはり一概に「相場」を挙げるのは難しいと言えるでしょう。
立ち退き料に含まれるもの
立ち退き料を算出するうえで、下記のような項目を考慮することもあります。
【住居使用の物件の場合】
・引越費用(引越し代、設備移転費、不用品処分費など)
・新居契約費用(敷金、礼金、保証料、仲介手数料など)
・家賃差額
・その他補償(迷惑料など)
【店舗使用の物件の場合】
・新店舗への移転費用(引越し代、店舗契約費、保証料、設備工事費、宣伝費など)
・家賃差額
・営業損失に対する補償(移転による休業中の営業補償、休業中の固定費、人件費など)
・借家権に対する補償
家賃や引越し代は地域によって金額が大きく異なるため、立ち退き料の金額は地域によっても差があると言えるでしょう。
立ち退き料がもらえないケース
立ち退きには、立ち退き料がもらえないケースも存在します。代表的なものが、「入居者の債務不履行がある」また「契約形態が定期借家契約である」場合です。
ケース1 入居者側に債務不履行がある場合
家賃を数ヶ月間支払わないなど、入居者側に債務不履行がある場合の立ち退きでは、立ち退き料は支払われません。大家は、債務不履行を理由に、契約解除を行うことができるためです。この契約解除については、借地借家法の範囲外であり、「正当の事由」も必要ありません。
ただし、債務不履行として立ち退きを求められる可能性があるのは、大家と入居者の信頼関係が損壊しているような場合に限られます。よって、一度の家賃不払い程度では、この対応が取られることは考えにくいと言えます。
ケース2 定期借家契約の場合
あらかじめ契約期間が限定されていて、満了時に更新しない旨が定められている契約形態を、定期借家契約と呼びます。この契約形態では、契約締結時に双方が更新しない旨に同意しているため、期間満了時の立ち退きにあたって立ち退き料が発生することはありません。入居者は立ち退き料なしで、契約内容のとおりにその物件から立ち退く必要があります。
ただし、定期借家契約であっても、大家側が再契約を了承すれば、そこに住み続けられる可能性はあります。
立ち退き料はいつもらえるのか
立ち退き料については、いつもらえるのかも気になる人が多いでしょう。
立ち退き料が支払われるタイミングは、原則建物の明け渡し時です。
入居者が退去してからの支払いだと、支払い義務がきちんと果たされない可能性があり、前払いだと期日が来ても入居者が物件を明け渡さなくなる恐れがあるためです。
明け渡し時の支払いが、入居者にとっても大家にとっても確実なのです。
ただし、双方で合意できた場合には、立ち退き料の支払いを明け渡し時以外に設定しても構いません。
立ち退きに際しては、引越しや新居契約などでまとまった金銭が必要です。これを自身で捻出するのが難しい場合もあるでしょう。そのような場合には、大家に立ち退き料の一部または全部の前払いを交渉してみるのもひとつの手です。
立ち退き料受け取りまでの流れ
立ち退きの一連の流れは、次の3つの段階から成ります。
①更新拒絶の通知・説明
②立ち退き交渉の実施
③建物の明け渡し・立ち退き料の受け取り
1 更新拒絶の通知
立ち退きにあたっては、まず大家側から更新拒絶の通知が行われます。
この通知は、借地借家法にて、契約期間満了の6ヶ月以上前に行わなければならないと定められています。6ヶ月未満のタイミングで通知があった場合、その立ち退き要請は認められません。
送られてくる立ち退き通知書には、立ち退きについての詳細が記されています。この内容については、必ずよく確認しておくようにしましょう。
2 立ち退き交渉の実施
次に、大家との立ち退き交渉に入ります。
立ち退きは、すぐに了承するのではなく一旦保留にして、必ず交渉を行うようにしましょう。
この交渉では、立ち退き料の金額やその他条件の希望などを大家に伝え、合意に向けて話し合いを行います。
交渉には知識も技術も必要になるため、弁護士に代理交渉を依頼することも検討しましょう。弁護士の手を借りることにより、入居者は自身の負担を軽減しながら、交渉をより有利に進められる可能性があります。
また、交渉が合意したら、合意書を作成し、大家と入居者双方が署名捺印を行います。
3 建物の明け渡し・立ち退き料の受け取り
入居者は、交渉で合意した期日までに、建物を明け渡します。建物からの退去が完了したタイミングで、大家から立ち退き料が支払われます。
立ち退き料を多くもらう交渉のポイント
最後に、立ち退き料をなるべく多くもらうために有効な4つの交渉ポイントについて解説します。
ポイント1 立ち退きの意思がないことを主張する
立ち退きを求められた時には、すぐに受け入れず、一旦は立ち退きの意思がないことを主張しましょう。
立ち退きでは、大家との心理的な駆け引きも重要です。すぐに立ち退きを受け入れれば、大家が自身の提示した以上の立ち退き料を支払うことはないでしょう。
しかし立ち退きを一旦拒否すれば、大家側は立ち退き料を上乗せしてでも、その入居者を立ち退かせようとするケースは少なくありません。
ポイント2 正当の事由の有無を確認する
前述のとおり、立ち退き要請には「正当の事由」が必要です。
実際に立ち退きを求められた際には、その理由が「正当の事由」に値するかどうか、よく検証しましょう。理由の正当性によって、支払われるべき立ち退き料の金額も変わるからです。
ただし、この判断を入居者自身が正しく行うのは困難です。
よって、この点については、不動産問題の実績豊富な弁護士に相談し、判断を仰ぐことをおすすめします。弁護士が「正当の事由」を検証すれば、より強い説得力で立ち退き料を請求することが可能になります。
ポイント3 立ち退きによる損害を主張する
立ち退きによって入居者がどれくらいの損害を被るか具体的に示すことも、交渉では有効です。引越し代や敷金・礼金、家賃など、その地域における同条件の物件の相場を確認し、交渉で大家に示しましょう。
「立ち退きにこれだけの費用がかかる」と理解できれば、大家側も納得感を持って、希望の金額の立ち退き料の支払いに合意する可能性があります。
立ち退き料の算定方法は、下記の記事にて詳しく解説しております。
立ち退き料の計算方法|引越し費用・家賃差額・迷惑料まで徹底解説
ポイント4 その物件の必要性を主張する
自分にとってのその物件の必要性を主張することも大切です。例えば、「家族に重病人がいて引越しにかなりの負担がかかる」「家族の人数が多く、なかなか条件に合う物件が他に見つからない」「引っ越すと店舗の得意客が離れてしまう」などです。
その物件ならではのメリットがある場合、入居者にとっての物件使用の必要性が高いと判断され、補償としての立ち退き料が増額される可能性があります。
まとめ
立ち退き料は、大家の「正当の事由」を補完するものです。よって、立ち退き理由やその他の状況によって、その金額は大きく変わります。
また、入居者が自身の権利や生活を守るためには、十分な立ち退き料を受け取ることが大切です。もし立ち退きを要請されたら、引越し代や家賃の相場を把握し、適切な金額の立ち退き料を請求するようにしましょう。
とはいえ、立ち退き料の請求や交渉は、入居者によって不安が大きく、負担にもなるものです。自身の負担を軽減しながら円滑に交渉を進めるには、不動産問題に強い弁護士への相談も検討しましょう。
エジソン法律事務所では、立ち退き料の増額請求に力を入れております。相談料0円で、立ち退きに関するご相談も承っております。
もし「提示されている立ち退き料が妥当かどうか分からない」などの質問がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
エジソン法律事務所・立ち退き料増額ホームページ:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢