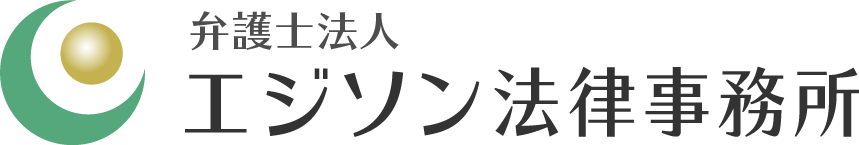コラム
大家都合で退去する場合の店舗の立ち退き料|相場・交渉ポイント等を解説

大家が入居者に物件からの退去を求めることを、立ち退きといいます。その対象は、住宅使用の物件に限りません。店舗使用の物件でも、立ち退きを求められることはあります。
では、店舗の立ち退きでは、テナント側はどれくらいの立ち退き料を受け取れるのでしょうか。また、納得のいく条件で立ち退くためには、交渉でどのような点に気を付ければ良いのでしょうか。
今回は、大家都合による店舗からの立ち退きについて、立ち退き料の相場や交渉ポイントなどをわかりやすく解説します。
なぜ大家都合の退去では立ち退き料がもらえるのか
まずは、「そもそもなぜ大家都合による物件からの退去では立ち退き料がもらえるのか」、その理由をみていきましょう。
立ち退きには「正当事由」が必要になる
建物や土地の賃貸借について定めた法律に、借地借家法があります。この法律では、立ち退きについても細かなルールが定められています。
その中でも、特に注目したいのが第28条「建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件」についてです。この条文では、賃貸人が賃借人に立ち退きを要請する場合には「正当の事由」が必要であることが記されています。
この正当事由は、大家と賃貸人双方の対象物件を使用する必要性の高さやその他の事情を総合的に判断して決めるものです。
多くの場合、店舗の賃貸人は営業を続けたいでしょう。
たとえ大家が「建物が老朽化しているから立ち退いてほしい」と一方的に要求しても、賃借人が物件の必要性やその他の事情を具体的に主張できれば、「立ち退きの正当事由が認められない」と判断され、立ち退き自体を拒否できるケースもあります。
また裁判で正当事由が認められた場合でも、賃借人は十分な立ち退き料を受け取って退去する場合が多いです。
立ち退き料は「正当の事由」を補完する
借地借家法第28条で「財産上の給付(=立ち退き料の支払い)が正当の事由の考慮要素になること」が記されているとおり、大家は立ち退き料を入居者に支払うことで、立ち退きの正当事由を補完することができます。
つまり、大家都合の立ち退きでは、「正当の事由」を補完する目的で、入居者に立ち退き料が支払われているのです。
また大家側としては、立ち退き料の支払いについて、「円滑に立ち退きへ協力してもらいたい」「入居者に補償したい」という思いもあるでしょう。
店舗の立ち退き料の算定要素
店舗の場合、立ち退き料の算定要素としては、次のようなものが挙げられます。
・新店舗への移転費用(引越費用、新店舗の契約費、新旧店舗の設備工事費など)
・家賃差額
・移転に伴う営業損失への補償
・借家権価格
立ち退き料の金額は、上記の要素をもとにそれぞれのケースごとに決められます。引越費用や家賃などは、店の規模や地域によっても大きな差が出るでしょう。
また、借家権とは、物件を借りている側が持つ権利のことを指します。立ち退きに際しては、この権利も補償の対象となることがあります。
店舗の立ち退き料の相場
店舗の立ち退き料は、住宅使用の物件の場合に比べ、高額になる傾向があります。
店舗の引越費用や新規契約費は、一般的な住宅の場合よりも高くなるでしょう。
ただし、店舗の立ち退きで支払われる立ち退き料の金額は、個々のケースによって大きく異なります。前述の算定要素をもとに、個別具体的な事情を考慮して、金額が決められるためです。
したがって、一概に「賃料の何年分」というような相場をお伝えすることが難しいです。
「提示されている立ち退き料は妥当なのか?」と不安な方は、弊所が過去に行った立ち退き料の増額事例を御覧ください。(店舗の事例も含まれています)
立ち退き料がもらえないケース
物件からの退去を要請されても、必ず立ち退き料をもらえるとは限りません。次のようなケースでは、立ち退き料の支払いが発生する可能性は低いと考えられます。
ケース1 賃貸借契約違反をしている
入居者が賃貸借契約に違反していた場合、債務不履行として、大家は契約を解除し、立ち退き料なしで退去を求めることができます。債務不履行解除による立ち退き要請は、借地借家法の問題ではなく、「正当の事由」も必要ありません。
ただし、一度家賃を滞納した程度でこの対応が取られることはまずないでしょう。債務不履行解除を行うためには、賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されていることがひとつの条件となるためです。
ケース2 定期借家契約
定期借家契約の場合も、退去にあたって立ち退き料は支払われません。
定期借家契約とは、契約時に更新しない旨があらかじめ決められている契約形態のことです。期間満了時の退去は契約時に双方合意しているはずなので、退去にあたって「正当の事由」は必要なく、立ち退き料の支払いも必要ありません。
ケース3 契約形態が賃貸借契約ではない
契約形態が賃貸借契約ではない場合でも、立ち退き料の支払いは発生しません。
例えば、業務委託契約や販売委託契約などの場合です。具体的には施設の一部を借りて店舗を運営している場合などが想定されます。
このような契約は、賃貸借契約とは別物です。よって、もし施設のオーナーが店舗に退去を要請しても、「正当の事由」の提示や立ち退き料の支払いは発生しません。
立ち退き交渉のポイント
ここからは、大家との立ち退き交渉で重要になる8つのポイントについてご説明します。
ポイント1 立ち退きによって生じる不利益を主張する
交渉では、物件から立ち退くことによってテナント側に生じる不利益を、大家にしっかり主張することが大切です。不利益に対する理解は、立ち退き料の金額やその他条件に影響するためです。
この不利益については、立ち退きによって発生する費用を具体的に提示して、数字として可視化するのも効果的でしょう。引越しにかかる費用や新店舗の契約にかかる費用、移転中の営業損失などを、その地域の相場や過去のデータから割り出して提示すれば、具体的にどれくらいの不利益が出るのか、理解してもらいやすくなります。
ポイント2 立ち退き料の性質を理解し適切な金額を請求する
立ち退き料の支払いは、法律で定められたものではありません。テナント側はそれを理解した上で、大家に適切な金額の立ち退き料を請求する必要があります。
例えば、もし大家に立ち退き料を支払う意思があるにも関わらず、テナントが妥当な金額に納得せず過剰な請求を続けてしまった場合、大家が立ち退き要請自体をあきらめ、立ち退き料の支払いそのものを取りやめてしまう可能性があります。
テナント側に法的な請求権はないため、そうなれば立ち退き料を受け取ることはできません。
このような事態を避けるためにも、立ち退き料の請求は、大家の支払能力や立ち退きを求める事情を加味して行うべきです。
ポイント3 退去する前に立ち退き料を請求する
立ち退き料の請求は、必ず退去する前に行いましょう。
大家は「正当の事由」の補完はもちろん、スムーズに立ち退きを進めるために立ち退き料を支払います。テナント側が要請を受けて早々に退去してしまえば、大家が立ち退き料を支払う理由はなくなってしまいます。
物件からの退去は、立ち退き料について合意した後に進めるようにしてください。
ポイント4 賃貸人が立ち退きを要請する理由を理解する
交渉にあたっては、大家がなぜ立ち退きを要請しているのか、その理由についても正確に知っておくことが重要です。理由ごとに立ち退きの緊急度には差があり、それによって請求できる立ち退き料の金額も違ってくるからです。
例えば、建物の建て替えの予定が迫っているような場合であれば、早急にテナントを退去させるために大家側が立ち退き料を上乗せしてくる可能性は十分に考えられます。
ポイント5 立ち退き交渉では金額以外も交渉する
立ち退き交渉で話し合うのは、立ち退き料についてだけではありません。その他の条件についても話し合い、希望を主張する必要があります。
例としては、物件の明け渡し日や立ち退き料支払いのタイミング、原状回復義務の取り扱いなどが挙げられます。
立ち退き料の支払いは明け渡し時に行われるのが通常ですが、交渉で合意できれば、一部または全部を事前に受け取ることも可能でしょう。
ポイント6 立ち退き交渉が決裂する可能性も認識しておく
立ち退き交渉は、必ず双方で合意できるわけではありません。時には交渉が決裂してしまうこともあります。
交渉決裂の場合、大家側が立ち退き要請を諦めるか、物件明け渡しの裁判に発展するかのどちらかになるでしょう。
裁判に発展した場合でもテナント側が立ち退き料を受け取れる可能性は十分にありますが、裁判には時間も費用もかかります。まずは双方の事情を互いに汲みながら、交渉での合意を目指しましょう。(もちろん裁判に移行し、時間をかけて適切な金額の立ち退き料を請求するのも、有効な戦略の一つです)
ポイント7 合意内容は書面で残す
交渉で合意した内容は、必ず書面に残しておくようにしましょう。口約束だけで合意内容を確認できるものがないと、後からトラブルに発展する恐れがあります。
書類は、決まった立ち退き料の金額やその支払い日、明け渡し日、遅延損害金についてなど、内容に漏れのないよう作成し、最後の署名時にはその内容を必ず見直すようにしてください。
ポイント8 弁護士に相談する
ご紹介したとおり、立ち退き交渉には気をつけるべき点が複数あります。しかし、これらの点に気をつけながら慣れない交渉を行うのは、テナント側にとって大きな負担となるでしょう。
そこで検討したいのが、弁護士への相談です。
弁護士の手を借りれば、テナント側は取るべき対応についてアドバイスを受けることができます。
また、法的知識と実務経験の豊富な弁護士が代理交渉を行えば、立ち退き交渉はより有利かつスムーズに進むでしょう。
納得いく条件で立ち退くためにも、弁護士への相談は有効です。
立ち退き料を受け取る際のよくある疑問
最後に、立ち退き料の受け取りに際して疑問に思う人が多いポイントを2つご紹介します。
Q1 立ち退き料は課税対象になりますか
受け取った立ち退き料は、所得金額に加算されます。よって、個人の場合であれば所得税、法人の場合であれば法人税の課税対象となります。
また、所得は「事業所得」「譲渡所得」「一時所得」などに分類されますが、立ち退き料の場合、その趣旨によって分類が変わります。例えば、営業損失の補填を目的とした場合であれば事業所得、借家権価格に対するものであれば譲渡所得に分類されるでしょう。
どの種類にあたるかは、ケースバイケースだと言えます。
Q2 敷金は返還されますか
立ち退きによる物件からの退去でも、基本的には通常の退去同様、敷金は返還されます。民法第622条にて、大家に対する敷金の返還義務が定められているためです。
よって、立ち退き時にテナント側が受け取れるのは、立ち退き料+敷金となります。
ただし、原状回復義務の取り扱いによって、実際の敷金の返還額は異なるでしょう。
立ち退き時の敷金の返還については、下記の記事にて詳しくまとめています。
まとめ
大家都合による店舗からの立ち退きでは、「正当の事由」の補完として、テナント側に立ち退き料が支払われます。
立ち退き料の「相場」はケースバイケースで、店舗の規模や地域などによって大きく異なります。
また、納得いく条件で立ち退くためには、立ち退き交渉が非常に重要な役割を果たします。この交渉には複数のポイントがあり、テナント側はこれに注意しながら交渉を進めなければなりません。
交渉を有利に進めるなら、不動産問題の実績豊富な弁護士に代理交渉を依頼しましょう。弁護士による交渉では、法律に基づいて適正な金額の立ち退き料を受け取れる可能性があるとともに、依頼者の負担も軽減できます。
エジソン法律事務所・立ち退き料増額ホームページ:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢