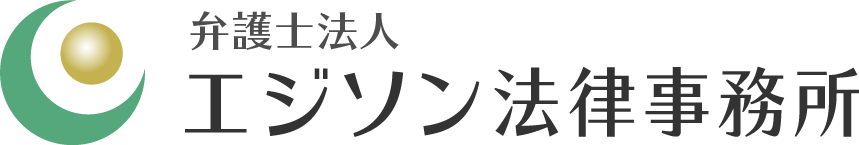コラム
工場からの立ち退き料の「相場」は?実際の裁判例も紹介

立ち退きとは「物件の貸主から借主に対し、住宅・土地からの退去を求めること」を指します。
立ち退きが行われるのは、住居目的の建物や土地だけではありません。事業を営むための店舗や工場であっても、立ち退きを求められることがあります。
立ち退きに際しては、それを求めた側から立ち退き料という名目で、金銭の支払いが行われるのが一般的です。
では、工場から立ち退きを求められたときに支払われる立ち退き料の「相場」とは、どれくらいなのでしょうか。
今回は、工場の立ち退き料の相場について、実際の裁判例や考慮すべき要素などとともに、わかりやすく解説していきます。
そもそも正当事由が無ければ立ち退く必要はない
立ち退きの通知を受け取ったときには、慣れない事態に戸惑う方が多いでしょう。中には、「急いで退去しなければ」と、焦って退去の準備を始めてしまう方もいるようです。
しかし、貸主による立ち退き請求に対し、借主が必ず従わなければならないとは限りません。立ち退き請求を拒否し、対象の物件を使用し続けられるケースもあります。
この判断にあたっては、「正当事由」が重要です。正当事由の有無によって、立ち退きに対応すべきかどうかは変わります。
立ち退きの「正当事由」
借地借家法第28条では、「賃貸人による賃貸借契約解約の申し入れは、正当の事由があると認められる場合でなければ行うことができない」旨が定められています。
ここでいう「正当の事由(正当事由)」の有無は、以下の事情から総合的に判断されることになります。
・建物の使用を必要とする事情(貸主・借主それぞれ)
・建物の賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況
・建物の現況
・財産上の給付(立ち退き料)
これらの事情を総合的に考慮し、立ち退きに正当事由が認められない場合、立ち退き請求は認められず、借主が物件から立ち退く必要もありません。
立ち退き請求に正当事由が認められる場合には、借主は物件から立ち退く必要がありますが、補償としての立ち退き料は支払われることが多いです。
ただし立ち退きの正当事由を厳密に検討するのは、あくまで裁判に発展した場合のみです。裁判前の交渉段階では正当事由の有無は関係なく、当事者が了解すれば立ち退きは完了します。
立ち退きの正当事由については、「【賃貸の借主向け】立ち退きの正当事由を弁護士が徹底解説」でより詳しく解説しています。
工場の立ち退き料の「相場」
立ち退きでは、貸主から借主へ立ち退き料の支払いが行われるのが一般的です。それは、住宅や店舗の場合だけでなく、工場の場合も同様です。
では、工場の場合、立ち退き料の相場とはどれくらいの金額なのでしょうか。
ただ実のところ、工場からの立ち退きにあたって支払われる立ち退き料に、明確な相場はありません。
立ち退き料の金額は「借主の経済的損失」を考慮して決められることも多いため、物件の規模や用途によって金額が大きく異なるのが実情です。
ここでいう「借主の経済的損失」とは、立ち退きがなければ発生し得なかった移転費用・営業損失などを指します。
工場の場合、住宅や店舗に比べ、代替物件の確保や機器の移設が困難であることから、借主の経済的損失は大きくなりがちです。その結果、立ち退き料は比較的高額になることが多いです。
参考として、エジソン法律事務所が実際に対応した「建設・工事系の作業場」の事例では、約850万円の立ち退き料を獲得したケースがあります。
(その他のエジソン法律事務所の立ち退き事例はこちら)
工場からの立ち退きの裁判例
ここからは、工場からの立ち退きに関する実際の裁判例を2つ確認していきましょう。
1690万円で工場の土地を明け渡した裁判例
賃借人Aは、借土地にて、製麺機を製造販売する工場を営むとともに、そこに居住していました。
しかし、当時の賃貸人は「Aは近い将来退去するから」という発言のもと、土地を新たな賃貸人Bに売却。Bは契約期間満了における更新拒絶を言い渡しましたが、Aは退去せず、裁判で争うことになりました。
賃借人側の事情
・当初は当該土地を自宅兼工場として使用していたものの、現在は主に商品置き場兼事務所となり、使用目的は限定的なものになっている
・事業は順調に拡大し、該当物件の他に建物や広い更地を購入し有している
賃貸人側の事情
・戦後の町づくりのため、周辺土地の一括利用により高層ビルを建設したいと考えている
・賃借人Aの賃貸借契約が満了となるまで待ち、その間も地代はごく低額で据え置きしていた
・正当事由の補強として、1,500万円の立ち退き料の支払いを申し出ている
判決
裁判所は、立地条件と日本の経済発展を考えると、昭和30年頃に建てた木造の2階建て建築物を倉庫・事務所として利用するだけでは、土地利用の効率が低いと判断。その上で、賃貸人Bはそもそも高層ビルの建設を予定して土地を購入しており、立ち退き料等の補償が相当なものであれば、正当の事由は認められるとした。
また、土地価格や変動率、借地権割合を踏まえると、BからAに支払われるべき立ち退き料は1,690万円が相応しいとして、BにはAへの1,690万円の支払いを、Aには当該土地の明け渡しを命じた。
参考:東京高等裁判所昭和51年2月26日判決(昭和49(ネ)2537号、判例集29巻1号16頁)
363万円で自宅兼工場を明け渡した裁判例
賃借人Aは、昭和47年ごろから賃貸人Bが所有する土地・建物に対して賃貸借契約を締結し、自宅兼プラスチック加工工場として使用してきました。
平成12年、BはAに対し、建物の老朽化や低廉な賃料を理由に、賃貸借契約の解約と物件の明け渡しを求めました。
賃借人側の事情
・対象の建物を自宅兼工場とし、年間売上約300万円のプラスチック成型加工業者を営む→自己使用の必要性が極めて高い
・賃貸人の賃貸借契約解約の申し入れには正当事由がない
・Bに対し契約に基づく建物の修繕義務の履行、土地の使用承諾、慰謝料の支払いを求める
(原判決では賃貸人から賃借人に立ち退き料363万円の支払いを決定したが、これを不服として控訴している)
賃貸人側の事情
・高齢の所有者(90歳超)が建物の老朽化による賃貸借契約の終了、建物の明け渡しを求めた
・該当の建物は現在構造的に不安定な状態にあり、建て替えの必要がある
・賃借人は、賃料5万円のところ一方的に4万円に変更し、長年4万円を払い続けていた
判決
裁判所は、当該建物の老朽化の進行、建て替えの必要性を認定。賃借人の使用必要性を一定程度認めながらも、賃貸人の建て替えの必要性が上回ると判断した。
また、立ち退き料を2,000万円程度が妥当であるとする賃借人の主張を認めず、原判決どおり賃貸人から賃借人に支払うべき立ち退き料を363万円とした。
(参考:東京高等裁判所平成15年1月16日判決(平成14(ネ)2577号))
工場の立ち退き料の考慮要素
工場の立ち退きで支払われる立ち退き料の金額は、ケースによって大きく異なります。その具体的な金額は、以下のような複数の要素を総合的に勘案して決められることになります。
①移転・内装工事にかかる費用
工場の立ち退き料では、工場を従来と同じように稼働できるように、工場を移転する費用および移転先の内装工事費用が考慮されます。
工場の場合、特殊な機械や設備が多いため、通常の引っ越し費用に加え、機械・設備移設費用が発生すると考えられます。また、特殊な設備で移転が困難であるようなもの、新設した方が安く抑えられるものであれば、その新設費用も立ち退き料として補償されることになります。
したがって、工場の移転・内装工事にかかる費用は、住宅や一般店舗に比べ高く、その分支払われるべき立ち退き料も高くなるのが一般的です。
②休業補償・営業補償
事業を行っている工場や店舗が立ち退く場合、移転に伴い、休業期間が発生します。この休業や移転における休業・営業補償も、立ち退き料では考慮されるべきです。
休業・営業補償では、休業中に損なう営業利益や人件費、その他固定費等が補償対象となります。また、移転による経営効率悪化ややむなく廃業した場合の損失に対する補償が行われる場合もあります。
③賃料の差額補償
移転先の工場の賃料が現在の賃料よりも高い場合には、その賃料差額も立ち退き料の中で補償されます。
とはいえ、立ち退き料による補償金額は、退去・移転前に決定・合意すべきものです。したがって、立ち退き料の交渉時に具体的な移転先を決めているケースはほぼなく、実際の移転先の賃料を把握することはできません。
そのため、賃料差額を算定するための移転先賃料は、現在の工場の規模や環境を踏まえ、同条件での移転を前提に、その条件での平均的賃料を用いることになります。
立ち退き料として請求できる「賃料の差額」の算出方法については、下記の記事にて詳しくまとめています。
立ち退き料として家賃の差額も請求できる| 算出手順も詳しく解説
立ち退き料の増額は弁護士へ相談を
工場からの立ち退きには、多額の費用はもちろん時間も手間もかかります。もし立ち退き料に関して交渉の余地があるのであれば、交渉の中でしっかり増額を要求する必要があります。
とはいえ、立ち退き料の増額交渉をうまく進めるには、法的知識や経験が必要です。
立ち退き問題を扱う弁護士に依頼すれば、交渉がスムーズに進む可能性は高くなります。
立ち退きトラブルにお困りの方、立ち退き料の増額を希望される方は、エジソン法律事務所へご依頼ください。立ち退き料増額の実績豊富な弁護士が代理交渉により、より良い条件を引き出せるよう尽力いたします。
無料相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢