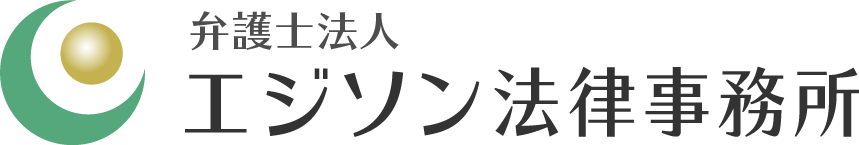コラム
立ち退きとは?もらえるお金や正当事由について弁護士がわかりやすく解説

「大家から急に、住んでいる賃貸物件から退去するよう言われた」
「契約更新拒絶の通知が届いたけど、どう対応すれば良い?」
などのご相談を受けることがあります。これらは「立ち退き」と呼ばれるものです。
部屋や土地を借りている場合、立ち退きのリスクは少なからず発生します。いざ立ち退きを求められたときに適切な対応を取れるよう、基本についてはしっかり理解しておくことが大切です。
そこで今回は、「立ち退き」の意味や正当事由、立ち退き料、手続きの流れまでわかりやすく解説します。
立ち退きとは
立ち退きとは「大家が借主に対し、建物から退去するよう求めること」を指します。
立ち退きは、建物の老朽化や大家の自己使用など、さまざまな理由によって行われます。
しかし、借地借家法上の「正当事由」が認められなければ、貸主の立ち退き要求も認められません。
また立ち退きの通知は、契約満了の6ヶ月前までに、借主に通知されていなければなりません。いきなり「3ヶ月後に立ち退いてください」などの要求は無効になります。
大家都合の立ち退きに際しては、貸主から借主に対し、立ち退き料が支払われるのが一般的です。
立ち退き料の金額を始めとした条件については、借主の権利や経済的損失を補償するためにも、貸主・借主間の慎重な交渉によって決める必要があります。
立ち退きに必要な正当事由とは
貸主が立ち退き要求を行うには、「正当事由」が必要です。
実際に、建物や土地の賃貸借について定めた借地借家法第28条には、「建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。」という旨が記載されています。
つまり「よほどの理由・事情がない限り、大家はみだりに入居者を追い出すことはできない」と法律で定められているのです。
正当事由は、主に以下の要素から総合的に判断されます。
・建物の使用を必要とする事情
・建物の賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況
・建物の現況
・財産上の給付(立ち退き料)
「建物の使用を必要とする事情」については、貸主と借主双方の事情が加味されます。
また、「財産上の給付」にあたる立ち退き料は、その他の要素を補完する役割を果たします。
貸主側の正当事由
「正当事由」として一定の必要性が認められることが多い、貸主側の「建物の使用を必要とする事情」には、以下のようなものがあります。
・建物の老朽化・建て替えの必要性
立退き理由として最も一般的なのが、「建物の老朽化に伴う建て替え」です。
築年数の経過により、安全性や機能性に不安が生じたことを理由に、明渡しを求めるケースが多く見られます。
ただし、実際には居住に支障がなく、雨漏りなどの重大な損傷もない場合、単に「古くなったから」という理由だけでは、正当事由として認められにくい傾向があります。
建て替えの必要性が具体的かつ合理的に示されていることが重要です。
・自己使用の必要性
次に「自己使用の必要性」です。
大家本人、またはその親族がその物件を使用したいという理由で立退きを求めるものです。
この場合、なぜその物件でなければならないのか、また、現在の借主を立ち退かせるほどの必要性があるかなど、事情の合理性が厳しく判断されます。
・収益性の低下
「賃貸経営上の採算が取れない」などの事情も、正当事由として考慮される場合があります。
たとえば家賃が相場よりも大幅に低く設定されている、修繕費や固定資産税などの維持費を賄えない、といった事情が該当します。
建物の維持・運営に過度な負担がかかっている場合、立ち退きを求める合理性が認められる可能性があります。
借主側の正当事由
借主にも、物件を継続使用する必要性や転居困難な事情がある場合があります。
代表的な例は以下のとおりです。
・使用の必要性
借主にとって「その物件でなければならない」という明確な理由がある場合、借主に有利な事情として働きます。例えば、以下のようなケースが該当します。
・近隣に同程度の条件・家賃の代替物件がない
・店舗で地域に根ざした営業を行っており、移転によって常連客を失うおそれがある
・長期間にわたり当該物件を使用しており、生活や営業の基盤となっている
・転居が困難
借主の年齢や家庭状況、健康状態などから転居が困難な事情がある場合も、借主に有利な要素となります。
・高齢者や障害のある方が居住しており、転居が困難である
・子育て中であり、環境が変わると子どもにとって影響が出てしまう
これら借主側の事情と、貸主側の事情を総合的に考慮し、最終的に「正当事由」があるかどうかが判断されます。
裁判にて、貸主側の正当事由が十分でないと判断された場合、「立ち退き料」の支払いをもって正当事由を補完できると結論付けられるケースも少なくありません。
立ち退き料とは
立ち退き料とは「立ち退きを要求した貸主から、退去する借主へ支払われる金銭」のことを指します。
(法的には「財産上の給付」と呼ばれています。)
立ち退き料は、正当事由の補完要素となります。
つまり裁判などにおいて「貸主に建物使用の必要性は認められるものの、借主の使用継続の必要性の方が上回る」と判断された場合、立ち退き料を支払うことで貸主側の正当事由が認められることがあります。
立ち退き料の決め方はケースによって異なりますが、基本的には「立ち退きによって借主が被る経済的損失」に応じて決まることが多いです。
立ち退き料に相場はない
立ち退き料の金額に、相場はありません。
具体的な金額は貸主・借主双方の事情、および立ち退きによって借主が被った経済的損失に応じて決まることが多いです。
他サイトではよく「立ち退き料の相場は、家賃の6〜12ヶ月分が相場(住居の場合)」と紹介されていますが、誤りです。
実際の金額はケースバイケースだと考えてください。
立ち退き料の具体例については、「当事務所が解決した実例」でもご紹介しています。
また、もし「提示された立ち退き料が妥当かどうかわからない・・・。」という方がいらっしゃいましたら、一度エジソン法律事務所にご相談下さい。相談料は無料でお受けしております。
エジソン法律事務所ホームページ:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
立ち退き料の考慮要素
すでにご紹介したとおり、立ち退き料の金額は、借主の経済的損失をもとに決められます。この経済的損失については、主に以下の要素が考慮されます。
・転居費用
・新居の契約費用
・家賃差額
・営業利益(店舗・事務所の場合)
・その他補償(迷惑料、借家権価格など)
これらの要素について、「借主が立ち退き後もそれまでと同じような生活を送ることができる」ことを前提に、立ち退き料は算出されます。
例えば転居費用であれば、これまでの住居と同程度の条件の住居に転居するための費用が考慮されます。
ただし、何ヶ月分の家賃差額が補償されるか、迷惑料としていくら補償されるかは、立ち退き交渉に大きく左右されます。交渉によっては非常に大きな金額になる可能性があります。
【注意】立ち退き料を請求できないケース
立ち退き料は、どんな場合でも請求できるわけではありません。以下のようなケースでは、基本的に立ち退き料を請求することはできません。
①すでに立ち退きに合意する書面にサインしている
物件の借主がすでに立ち退きに合意する書面にサインしてしまっている場合には、立ち退き料は発生しない可能性が高いです。
立ち退き料は、円滑な立ち退きのために支払われるものです。借主がすでに立ち退きに正式合意している場合、貸主にとって、立ち退き料を支払う必要性はなくなってしまいます。
②家賃滞納など重大な契約違反がある
家賃滞納や契約外目的での使用など、借主に重大な契約違反がある場合、貸主は賃貸借契約を強制解除することができます。この場合も、立ち退き料は支払われません。
家賃滞納の場合、1ヶ月程度で強制解除となることはまずありません。しかし、滞納が3ヶ月程度続いた場合には、信頼関係が破壊されたとみなされ、強制解除されることがあります。
③すでに転居してしまっている
借主がすでに転居してしまっているという場合にも、立ち退き料は支払われません。それは、貸主が立ち退き料を支払う理由がなくなってしまうためです。
立ち退きでは転居を急がず、立ち退き条件について合意するまでは、転居先の候補物件をリサーチする程度にとどめておくことをおすすめします。
④定期借家契約・定期借地契約である
あらかじめ契約を更新しないことが決まっている定期借家契約・定期借地契約の場合も、立ち退き料は支払われません。
ただし、契約を定期借家契約・定期借地契約とするには、契約書面に定期借家契約・定期借地契約であることや契約期間が明記されていること、また契約締結時に契約を更新しない旨が借主にきちんと説明されていることなど、条件があるため注意が必要です。
立ち退きの流れ
立ち退きの手続きは、以下のような流れで進めていきます。
・立ち退き通知
・弁護士への相談・依頼
・立ち退き料の調査・計算
・貸主との交渉
・裁判
・物件の明け渡し、立ち退き料の支払い
立ち退きでは、まず貸主から借主へ、契約更新拒絶の旨が通知されます。また通知日から明け渡し日までに、最低6ヶ月間の猶予期間が必要です。
立ち退きの一連の手続きには、法的な知識が求められます。したがって、立ち退き通知を受けた場合には、借主は不動産問題を扱う弁護士に相談し、サポートを受けることをおすすめします。
次に、立ち退き料の調査・計算に入ります。転居費用や家賃差額などの具体的金額を算出し、最終的な立ち退き料の金額を決めましょう。
その後は、立ち退き料を始めとした条件をすり合わせるため、貸主側と交渉を行います。ここで粘り強く、また説得力のある交渉ができるかによって、立ち退き料の金額は大きく変わります。より良い内容で交渉を進めるには、弁護士に代理交渉を依頼しましょう。
交渉で合意できれば合意書を作成し、物件の明け渡し、立ち退き料の支払いをもって、立ち退きは終了です。
しかし、交渉で合意できなければ、裁判で解決を目指すケースもあります。
よくある質問
最後に、立ち退きについてよくある質問について、その回答をご紹介します。
大家都合の立ち退きは拒否できる?
大家都合の立ち退きは、拒否できるケースがあります。大家が主張する立ち退き理由が正当事由として十分でない場合、借主が物件から立ち退く必要はありません。詳しくは、「立ち退き請求を拒否して居座ることは可能?」を参考にしてください。
正当事由の該当性を判断するには立ち退き問題に関する法的なノウハウが必要です。正当事由が認められるかどうかの判断は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するタイミングは?
立ち退き問題について弁護士に相談するタイミングは、貸主との交渉前が好ましいです。交渉やその準備には法的知識が必要になるためです。
このタイミングであれば、弁護士が交渉準備を行い、代理交渉を行うこともできます。
敷金の返還を拒否されたら?
敷金の返還については、法律で定められています。立ち退きであっても、物件からの退去時には、賃貸借において生じた債務の額を除いた敷金の残高を、貸主は借主に返還しなければなりません。
原状回復などの費用を差し引いて敷金の残高があるにもかかわらず、貸主が敷金を返還しない場合、その対応は違法であるということになります。弁護士に相談し、しかるべき対応を取りましょう。
中には「立ち退き料に敷金も含まれる」と主張する貸主もいますが、敷金と立ち退き料は別物です。
立ち退き時の敷金返還については「大家都合で立ち退きする場合、敷金は返還されるのか?」にて詳しく解説しています。
立ち退き料の増額は弊所へ相談を
立ち退き料増額のための交渉は、エジソン法律事務所へご依頼ください。立ち退き料の増額に多くの実績を持つ弁護士が、依頼者様に代わって力強く交渉を行います。
また、弊所では完全成功報酬制を採用しております。
初期費用は0円、立ち退き料が発生しなければ、報酬も発生しません。
初回相談料は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから:問い合わせフォーム
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢