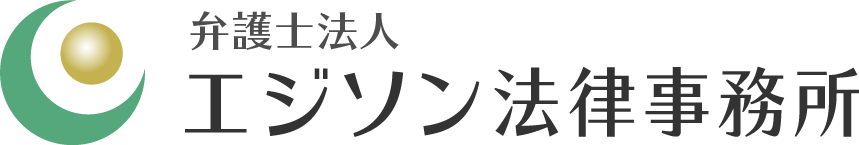コラム
立ち退き料の計算方法|引越し費用・家賃差額・迷惑料まで徹底解説

マンション・アパートなどの賃貸物件に住んでいると、大家から立ち退きを命じられることがあります。この時、大家から「立ち退き料」が支払われることがあります。
この立ち退き料の金額には、法律上の基準や計算式はありません。支払われるべき金額は、個別の事情によって大きく異なります。
ただし、立ち退きによって借主が被る経済的損失を項目ごとに計算したり、借家権を元に計算したりすることで、おおよその金額を算出することは可能です。貸主への立ち退き料の請求においても、これらの方法を根拠に挙げ、交渉を進めていくやり方が合理的です。
そこで今回は、貸主都合による立ち退き料の算定方法について、わかりやすく解説していきます。立ち退き要求を受けた際にお役立てください。
立ち退き料の意義
最初に立ち退き料が発生する理由や、その意義について解説します。
建物や土地の立ち退きについて定めた借地借家法には『貸主が賃貸借契約の解約を申し入れるためには、「正当の事由」が必要である』という旨が記されています。この正当事由は、以下のような要素を総合的に考慮して判断されることになります。
・貸主および借主が建物の使用を必要とする事情
・建物の賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況
・建物の現況
・貸主による財産上の給付
このうち最後に挙げた「財産上の給付」が、立ち退き料と呼ばれるものです。
立ち退き料はあくまで他の要素を補完するものとして存在しています。つまり高額な立ち退き料を支払われても、大家が物件を使用する必要性が客観的に認められなければ、立ち退き自体が認められないのです。
(ただし、当事者間の交渉による合意であれば、必ずしも正当事由が必要であるわけではありません)
貸主が建物を必要とする事情(老朽化による建て替えなど)と、借主の事情(住み続けたい理由など)が均衡した場合に、立ち退きを成立させるべく支払われるのが、立ち退き料だと考えると良いでしょう。
立ち退き料の「相場」は?
立ち退き料の「相場」は「住居使用の物件の場合:家賃の6〜12ヶ月分程度」「店舗使用の物件の場合:家賃の2〜3年分程度」と説明されることが多いです。しかし、これは誤りです。
これらの「相場」はあくまで目安であり、立ち退き料に明確な相場は存在しません。
そもそも「必ず立ち退き料を支払わなければならない」という法律上の決まりはなく、支払う場合でも「賃料の何カ月分」「土地価格の何割」などといった明確なルールや計算式が設定されているわけではありません。
立ち退き料の具体的な金額は、貸主・借主の事情を踏まえ、ケースごとに判断していくことになります。交渉を行う弁護士の経験によっても立ち退き料の金額は変わるため、代理交渉の依頼は実績豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
もし「提示されている金額が妥当なのか知りたい」という場合は、過去の立ち退き料請求の事例をご覧ください。たとえ住居使用のアパートでも、立ち退き料が賃料の数年分になるケースもあれば、そうでないケースもあるのです。
立ち退き料の算定方法
賃貸物件などからの立ち退きにあたって支払われる立ち退き料の金額は、立ち退きによって借主が被る経済的損失、もしくは借家権の金額をもとに算定します。
ここでは「移転に伴う損失を合計する方法」と「借家権割合方式で計算する方法」の具体的な手順を解説します。
①移転に伴う損失を合計する方法
立ち退き料の算定のもっとも一般的な方法が、立ち退きによる移転によって借主が被る具体的な損失を合計し、それを立ち退き料とする方法です。「立ち退きによって発生する費用を払ってほしい」というシンプルな理屈であり、説得力があります。
移転に伴う損失の項目としては、以下のようなものが考えられます。
・引越し費用
・新居の契約費用
・家賃差額
・迷惑料
・その他の補償(店舗の場合)
項目ごとに確認していきましょう。
引越し費用
立ち退くことになった借主は、新居を探して引越しを行わなければなりません。引越しには、引越し業者への依頼費やエアコン等設備の移転費用、不用品の処理費用などが発生します。
これらの費用は、立ち退き料の一部として算定すべきものです。
このうち、引越し業者への依頼費については、同条件で複数の引越し業者から見積もりを取り、地域や時期による費用差額も勘案しながら、妥当な金額を割り出します。
店舗の立ち退きの場合、設備移転には多額の費用がかかるため、引越し費用の項目はかなり高額になるでしょう。
新居の契約費用
住居や店舗の移転では、新居・新店舗の契約費用も発生します。具体的には、敷金・礼金、仲介手数料、保証料などが該当します。
これらの費用については、退去する物件と同条件の物件の相場から決定するのが一般的です。
賃貸の初期費用は、一般的には家賃の5カ月分程度が相場となるので、決して金額は小さくありません。それが店舗となれば、敷金(保証金)や前家賃などがそれぞれ数カ月発生し、必要な初期費用は数百万円にものぼる可能性があります。
これは借主にとって大きな経済的損失であり、立ち退き料でしっかり補償されるべきです。
家賃差額
家賃差額とは「住んでいる物件の家賃と、移転先の家賃との差額」のことです。もし退去する物件の家賃が10万円で、移転先の物件の家賃が12万円なのであれば、「家賃差額の2万円×一定期間分」が立ち退き料に含まれることになります。
どれくらいの期間分、家賃差額が補償されるかは、ケースによって異なります。数カ月であることもあれば、数年分補償されることもあります。この補償期間は交渉によって大きく変わるため、弁護士に任せることをおすすめします。
家賃差額の算出方法ついては、「立ち退き料として家賃の差額も請求できる| 算出手順も詳しく解説」でより詳しくご説明しています。
迷惑料
立ち退きによって、借主は多大な迷惑を被ることになります。引越しには労力が必要ですし、新しい物件探しにも手間がかかるでしょう。場合によっては、引越し後に通勤・通学時間が長くなったり、急な環境の変化に戸惑ってしまったりする方もいるはずです。
このような損害(精神的苦痛)に対する迷惑料・慰謝料も、立ち退き料として請求できる項目の一つです。実務経験上、交渉次第では、この迷惑料が最も金額が大きい項目になることも少なくありません。
借主が病気であったり高齢であったりして引越しに大きな負担が伴う場合には、金額が上乗せされる可能性もあります。
迷惑料の交渉のコツについては「立ち退き料に迷惑料は含まれる?内訳や交渉のコツを解説」にて解説しています。
その他の補償(店舗の場合)
立ち退くのが住居ではなく店舗である場合には、立ち退き料として営業補償を請求することも可能です。店舗の営業補償には、以下のような項目が含まれます。
・従業員への休業手当
・休業期間中の法人税、所得税、住民税など
・休業期間中の収益減
・常連客がいなくなることへの補償
・経営効率悪化に対する補償
・その他店舗移転に伴う費用
上記の項目は、国土交通省の「公共用地の取得に伴う損失補償基準」が根拠になっています。この基準では、「第44条 営業休止等の補償」として、以下の内容が示されています。
土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。
一.通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
二.通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては所得減)
三.休業することにより、又は店舗等の位置を変更することにより、一時的に得意を喪失することに よって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)
四.店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額
(参照:国土交通省「公共用地の取得に伴う損失補償基準 第44条 営業休止等の補償」)
上記は公共用地の立ち退きに関するものですが、一般的な立ち退きにおいても参考にすべき基準です。
店舗の立ち退き料を算出する際は、上記を根拠に従業員への休業手当や税金等の補償を請求することがあるため、覚えておきましょう。
②借家権割合方式で計算する方法
立ち退き料の計算では、借家権割合方式という方法を用いることがあります。具体的な方法について見ていきましょう。
借家権価格とは?
借家権とは、借主がその物件を借りる権利を指す言葉です。この権利を財産的価値に数値化したものが、借家権価格となります。
また、立ち退き料の算定にあたって、この借家権価格を基準に計算を行うのが、借家権割合方式です。
借家権割合方式は、計算がわかりやすい点がメリットです。
一方で「そもそも第三者との取引対象にならない借家権を基準とすることに説得力がない」「借りた期間が考慮されない」「この価格に相当する権利を、なぜ借主が持っていることになるのか根拠が乏しい」などの問題点もあります。
過去の判例では、借家権割合方式を採用したケースも、否定したケースもあることから、その利用可否はケースバイケースだといえるでしょう。
借家権割合方式の計算式
早速、計算式を見てみましょう。
【借家権割合方式の計算式】
借地権価格×0.3+建物価格×0.3=借家権価格
大雑把に計算する場合は、借家権割合を30%に設定することが多いです。
借家権割合方式では、借地権価格の30%と建物価格の30%を合算して、借家権価格を算出し、これを立ち退き料の参考とします。
この計算式を利用した場合、物件によっては、かなり高額な金額が算出されるケースもあります。
ただし、借家権割合方式を採用した過去の判例を見ても、実際の判決では算出金額を何割かに減額し、立ち退き料とするケースが多く見られます。
注意:立ち退き料が発生しないケース
立ち退き料は、必ず発生するとは限りません。
以下のような場合には、借主は、物件から退去しても立ち退き料を受け取ることはできません。
・定期借家契約の期間満了を迎えた場合
・借主に契約違反や迷惑行為があった場合
・物件が競売にかけられた場合
定期借家契約は最初から契約期間が決まっている契約です。契約期間が満了になっても契約は自動更新されず、立ち退き料は発生しません。
また借主に問題行為があった場合に行われる賃貸借契約の強制解除の場合、また競売の落札者による立ち退き要求の場合も、立ち退き料は支払われないと考えられます。
立ち退き料が発生しないケースについては、下記の記事で詳しく解説しています。
「立ち退き料がもらえないケース / 大家都合で退去する場合の立ち退き料の相場」
よくある質問
最後に、立ち退きにあたって借主からよく受ける質問とその回答をご紹介します。
立ち退きでも原状回復は必要ですか?
賃貸借契約において、借主は、退去時に物件を借りたときの状態で返却する義務を負います。これが、「原状回復義務」です。
立ち退きによる退去の場合でも、原状回復義務はなくなりません。経年劣化によるもの以外の傷や汚れなどは、借主が修繕費用を負担する必要があります。
ただし、立ち退き交渉によって、原状回復義務の免除を求めることは可能です。
(そもそも、老朽化による建て替えを目的とした立ち退きである場合、取り壊すのであれば原状回復の必要性は低いはずです。)
実際にエジソン法律事務所では、お引き受けしたほとんどの事例において、原状回復義務の免除で合意しています。
敷金は戻ってきますか?
敷金の返還は、民法で規定された決まりです。貸主は、家賃の滞納分や原状回復に伴う修繕費用を除き、敷金の残額を必ず借主へ返還しなければなりません。
中には「立ち退き料に敷金が含まれている」と主張する貸主もいるようですが、立ち退き料と敷金は別物です。必ず立ち退き料とは別に、敷金の返還を請求するようにしましょう。
立ち退き料の増額交渉はエジソン法律事務所へ相談を
「急に大家から立ち退きを求められた」「立ち退き交渉の代理を依頼したい」という方は、エジソン法律事務所へご相談ください。多数の立ち退き料増額実績を持つ弁護士が、然るべき補償を得るべく、交渉をはじめとした手続きをサポートします。
弊所は完全成功報酬制を採用しており、初回相談料・着手金は0円。立ち退き料が発生していなければ、成功報酬も発生しません。
立ち退き料は、交渉次第で増額させることが可能です。住居・店舗からの思いがけない退去に対して十分な補償を受けるためにも、ぜひ弊所への依頼をご検討ください。
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢