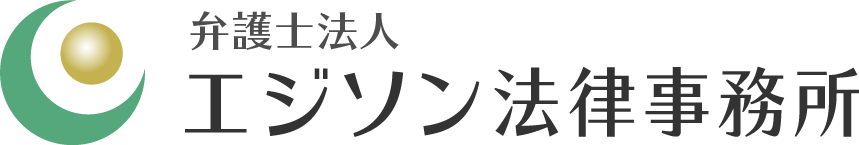コラム
大家から退去命令が来た時の猶予期間|とるべき4つの行動について解説

賃貸物件に住んでいると、大家から退去命令を受ける可能性があります。そして、その理由や状況によって、入居者が取るべき対応は異なります。
では、大家からの退去命令はどのような場合に認められるのでしょうか。
また入居者は退去命令に対し、いつまでにどのような対応を取るべきなのでしょうか。
今回は、大家からの退去命令が認められる条件とその対応、また退去までの猶予期間について、わかりやすく解説します。
そもそも大家からの退去命令は法的に認められるのか
大家からの退去命令は、どんな場合にでも認められるわけではありません。法的に問題なく退去命令を出すには、一定の条件を満たす必要があります。
大家が入居者に退去命令を出すケースは、大きく「借主に賃貸借契約違反がある場合」と「大家の都合で入居者に退去してほしい場合」の2種類に分けられます。
ここでは上記2つの場合において、大家の退去命令が認められるための条件をみていきましょう。
借主に賃貸借契約違反がある場合
借主である入居者が賃貸借契約に違反している場合、大家からの退去命令は認められる可能性が高いです。
入居者の賃貸借契約違反の例を下記に挙げます。
・一定期間以上の家賃滞納
・物件の破壊・汚損
・騒音・異臭
・ペット不可物件でのペット飼育
・契約と異なる用途での使用
・大家に無許可でのリフォーム など
このような行為は通常、賃貸借契約書に禁止の旨が明記されているかと思われます。
借主の契約違反は賃貸借契約の解除理由となるため、大家の退去命令は認められる可能性が高いです。
大家の都合で入居者に退去してほしい場合
入居者に契約違反がなく、大家が自身の都合で退去を求めるケースもあります。
ただし、このようなケースの立ち退きは、どのような場合でも認められるものではありません。大家の勝手な理由での退去が可能になれば、入居者の権利は守られないでしょう。
大家都合の立ち退きの場合、大家が退去命令を行うには必ず次の2つの条件を満たさなければなりません。
①明渡し希望日の1年~6カ月前までに通知する
賃貸借契約について定める借地借家法には、契約更新について次の記載があります。
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす
(e-Gov法令検索 「借地借家法第26条」)
つまり、大家が自己都合で入居者に物件からの退去を請求する場合には、賃貸借契約期間満了の最低6カ月前までに、その旨を通知しなければならないのです。
もし大家から指定された立ち退きまでの期間が6ヶ月よりも短い場合、借地借家法に違反していることになるため、有効な立ち退き要請であるとは言えません。
②正当事由(立ち退き料などを含む)が必要
大家が自己都合で入居者に物件からの退去を求めるためには、正当事由が必要です。
これは借地借家法第28条で定められているもので、正当事由の有無は以下のような要素を総合的に勘案して判断されます。
・大家がその物件を使用する必要性の高さ
・入居者がその物件を使用する必要性の高さ
・立ち退き料の支払いの有無とその金額
借地借家法第28条では「財産上の給付」、つまり立ち退き料の支払いが正当事由を認める考慮要素になることが記されています。
借地借家法は、賃借人である入居者の権利保護に重きを置く法律です。よってただの老朽化や自己使用など、特別に緊急性のない理由では、多くの場合「大家がその物件を使用する必要性の高さ」は十分とされず、正当事由として認められにくいです。
このような場合、大家は入居者に立ち退き料を支払い、正当事由を補完するケースが少なくありません。
大家からの退去命令で立ち退き料はどのくらいもらえるのか
家賃の不払いなどの契約違反がなく、明らかな大家都合の立ち退きである場合、立ち退き料が支払われることがあります。
他サイトでは「立ち退き料の相場は家賃の6〜12カ月分」だと言われていますが、これはあくまで相場であり、実際の金額は個々の状況によって大きく異なります。
弊所の立ち退き料請求の事例を見ても分かりますが、結果的に家賃の数年分になるケースもあれば、そうでないケースもあります。
また立ち退き料を算出する場合、次の項目が考慮要素になることもあります。
・転居費用(引越し費用、設備撤去費用、不用品処分費用など)
・新居契約費用(敷金、礼金、保証料、仲介手数料など)
・家賃差額(数カ月〜数年分)
・その他補償(迷惑料)
・営業利益(テナントの場合)
特に迷惑料については、ケースによる金額の差が大きくなる傾向があります。つまり立ち退き交渉において、迷惑料は立ち退き料の金額を左右する非常に重要なポイントだといえるでしょう。
大家から退去命令の通知が来たときにとるべき4つの行動
ここからは、大家から退去命令の通知が来た場合の対応について解説します。
1. 通知書の内容と正当事由を確認する
入居者は、まず通知書の内容を確認するようにしましょう。
賃貸物件からの退去を求める際には、通知日から明渡し日までの間に最低でも6カ月以上の猶予が必要です。
そして記載されている退去を求める理由が、正当事由に該当するものであるのかどうかを確認しましょう。
正当事由なしに、大家は入居者に退去を要請することはできません。また、大家が提示した理由によって、支払われる立ち退き料の金額も変わることが多いです。
退去にあたって適切な補償を受けるためにも、入居者は正当事由に足る退去理由が通知書に記載されているかを確認しましょう。
2.賃貸借契約書の内容を確認する
通知書を受け取ったら、物件を借りる時に交わした賃貸借契約書の内容の見直しも行いましょう。
例えば、次のような契約の場合、基本的に立ち退き料の請求はできないケースが多いです。
・定期借家契約
・一時使用目的の賃貸借契約
・取り壊し予定の建物の賃貸借契約
上記のケースでは、契約の時点で期間満了時の退去が決められています。そのため立ち退き料は発生しないことが多いです。
また入居者の契約違反によって命じられた退去の場合も、大家から立ち退き料が支払われることはありません。
3.大家と交渉する
大家から退去を求められたら、すぐに了承するのではなく、必ず交渉を行うようにしてくだい。
交渉では、立ち退き料の金額やその他の条件などを話し合い、双方での合意を目指します。
住んでいる物件からの退去は、入居者にとって大きな負担になるものです。よって、交渉ではしっかりと要望を主張し、適切な補償を得なければなりません。
交渉では立ち退き料の金額はもちろん、その支払いのタイミングや退去期日などについても話し合うようにしましょう。
4.弁護士に相談する
大家から退去を求める通知を受けた時には、弁護士への相談も検討しましょう。
退去通知を受け取った後には、入居者は通知書の内容を確認し、大家と交渉を行わなければなりません。
しかし、この作業には法的な知識や交渉の技術が必要です。入居者が個人でこれを行うとなると、そのハードルは決して低いとはいえないでしょう。
そこで手を借りるべきなのが、法律の専門家である弁護士です。
弁護士は、法律の知識と経験を生かして大家の主張する「正当の事由」を正しく判断するとともに、高い交渉力によって適切な立ち退き料の支払いを求めることができます。代理交渉を弁護士が担うことにより、入居者自身の負担も大きく軽減されるでしょう。
エジソン法律事務所では、立ち退き料の増額交渉のご相談も承っております。
大家からの退去命令を無視したらどうなる?
ここからは、大家からの退去命令を無視したらどうなるのか、退去に応じないことは可能なのか解説していきます。
借主に賃貸借契約違反がある場合
借主である入居者が賃貸借契約に違反している場合、貸主である大家は契約違反を理由に、入居者を立ち退かせることができます。
そのため、基本的に退去命令を無視することはできません。もし無視を続けた場合、最終的には強制執行を受ける可能性があります。
大家の都合で入居者に退去してほしい場合
大家都合で退去を求められた場合、「正当の事由」が無い限り、入居者が退去を拒否することは可能です。
また通知日から明渡し希望日までの間に、6カ月以上の猶予期間がない場合にも、入居者が退去命令に従う必要はありません。借地借家法第26条にて、「契約賃貸借契約期間満了の最低6カ月前までに更新しないことを通知しなければならない」旨が定められているためです。
普通賃貸借契約でこの通知がなかった場合、法定更新として、契約は今まで通り更新されることになります。
ただし、退去に応じない場合でも、通知を完全に無視するのはおすすめできません。物件から強制退去させられてしまう恐れがあるためです。
退去に応じない場合は、その旨をきちんと大家に伝えるようにしましょう。
まとめ
大家からの退去命令には、「入居者の契約違反によるもの」と「大家都合によるもの」の2種類があります。このうち、大家都合での退去については、「正当の事由」と立ち退き料の支払いが必要です。
また退去通知は、指定された退去日までに6カ月前の猶予が必要です。
そして支払われるべき立ち退き料の金額は、ケースによって大きく異なります。適切な補償を受けるためにも、立ち退き料を決める交渉は不動産問題を取り扱う弁護士に相談しましょう。専門家の手を借りることで、入居者個人の負担は軽減され、また有利な条件での合意も目指せます。
エジソン法律事務所では、相談料・着手金無料で立ち退き問題に関するご依頼を承っております。立ち退きに関してお困り事がありましたら、まずはお気軽に無料相談をお申し込みください。
エジソン法律事務所・立ち退き料増額ホームページ:https://edisonlaw.jp/tachinoki/
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢