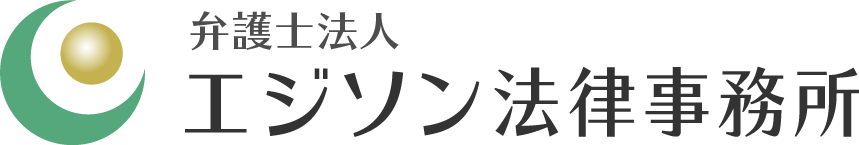コラム
道路拡張による立ち退き、いくらもらえる?立ち退きの流れ等も解説

都市計画・開発では、街の環境整備を行うために、都市計画道路の拡張工事を実施することがあります。この時、道路の拡張にあたって障害となる建物がある場合には、その建物を取り壊すため、そこに住む住民は行政側から立ち退き要請を受けることになります。
では、道路拡張のための立ち退きでは、そこに住む住民はいくらの金額の立ち退き料をもらえるのでしょうか。
また、立ち退き要請を拒否することはできるのでしょうか。
今回は、道路拡張による立ち退きについて詳しく解説します。
道路拡張による立ち退き料の相場
行政側から道路拡張のための立ち退きを求められた場合、住民は自身の所有する土地や建物から退去しなければなりません。この時、損失を補償するため、住民には行政から立ち退き料が支払われます。
ここでは、その金額の相場についてみていきます。
道路拡張により土地を失う場合の立ち退き料
道路拡張により土地を失う場合の立ち退き料は、ケースバイケースです。
なぜなら、道路拡張による立ち退きで支払われる立ち退き料の算出に用いられるのは、土地の公示価格や基準地価だからです。
土地の公示価格や基準地価には、地域によって大きな差があります。その地域の公示価格・基準地価に、立ち退きによって住民が失う土地の面積をかけたものが、立ち退き料の基本の金額となります。
例を挙げてみましょう。
公示価格が1㎡あたり25万円の地域での立ち退きで、住民が150㎡の土地を失うとします。この場合、この住民が受け取れる立ち退き料のベースは、3,750万円(25万円×150㎡)です。
この計算式による金額をベースに、迷惑料などが加算されたものが、実際に支払われる立ち退き料となります。
さらに、失う土地上に塀や樹木等の工作物がある場合には、それらの補償も立ち退き料に含めることが可能です。
また、土地の損失補償に加算される迷惑料も、個々の事情によって金額が大きく異なります。その土地を失うことで負う住民の不利益が多いほど、迷惑料として支払われる金額は大きくなるのが合理的でしょう。
道路拡張により持ち家を失う場合の立ち退き料
道路拡張の範囲内の土地上に建物が立っている場合には、土地が収用されるだけでなく、建物も取り壊されることになります。つまり、そこに住む住民は土地だけでなく、持ち家も失うことになってしまうのです。
この場合、住民は前述した土地の補償に加え、持ち家に対する補償も受けることができます。この補償の対象となるのは、次のような費用です。
・現在建っている建物を取り壊す費用(解体費、廃材処分費など)
・建物の再建築にかかる費用
・住民の転居費用
・再建築する建物が完成するまで住民が居住する賃貸物件の費用
この場合に補償されるのは、現在の持ち家と同等の建物を再建築するのに必要な費用です。立ち退きにあたって、現在の持ち家よりも構造のランクが高い建物や設備が充実した建物を建てようとしても、現在の持ち家以上の費用は補償されないので注意しましょう。
また、転居費用や一時的な賃貸物件の居住費用などは、その地域やその時期の相場をもとに算出されます。
道路拡張による立ち退きの流れ
道路拡張による立ち退きは、次のような流れで進められます。
①道路拡張計画の策定
②住民への説明
③調査・資金調達
④立ち退き交渉の実施・合意書の作成
⑤住民の退去・立ち退き料の支払い
各手順の内容について詳しくご説明します。
1 道路拡張計画の策定
道路拡張にあたってまず行われるのが、工事を行う行政による計画策定です。行政は、道路の需要や安全性、人口の変化など様々な要素を考慮して、綿密な道路拡張計画を立てていきます。
また、計画に基づき、現地調査や事前測量、図面作成なども進められます。
2 住民への説明
道路拡張の計画や方針が決まったら、その地域の地権者である住民や自治体に対する説明が行われます。
この時、住民側は拡張計画の内容やそれによる影響、補償の方針などについて行政側にしっかり確認し、後の交渉に備えるようにしましょう。
3 調査・資金調達
地権者や自治会への説明後には、行政は現況測量調査や用地測量調査、そしてその評価を行います。これらの調査は、立ち退き対象の土地を確定するために必要なものです。
また、行政は工事のための資金調達も進めていきます。工事の財源になり得るのは、国庫補助金や都道府県支出金、市町村支出金などです。
4 立ち退き交渉の実施・合意書の作成
立ち退き対象の土地が確定したら、その土地の住民と行政との間で立ち退き交渉を実施します。
この交渉では、立ち退き料の金額や住民の退去時期、条件などについて話し合います。この時、より良い条件を引き出すためにも、住民は行政側の提案をすぐに受け入れるのではなく、慎重に検討するようにしましょう。
弁護士に代理交渉を依頼することも検討すると良いでしょう。
なお、立ち退く土地や建物を賃貸物件として貸し出している場合、賃借人である入居者の立ち退き時期も考慮する必要があることを認識しておきましょう。
双方が条件に合意すれば、その内容をまとめた合意書を作成し、署名します。署名前には、交渉の内容がきちんと反映されているか、合意書の文章をよく確認するようにしてください。
5 住民の退去・立ち退き料の支払い
交渉後には、住民は決められた期日までに退去できるよう、引越しや賃貸契約などの手続きを行います。
また、失う土地については、土地の分筆や所有権の移転などの登記関連手続きが必要です。これらの手続きについても、弁護士のサポートを受けると良いでしょう。
立ち退き料は、通常、住民の退去後に支払われます。
ただし、引越しや新居の契約には費用がかかります。立ち退き料の先払いを希望する場合には、その旨を交渉時に伝えるようにしてください。
地域の住民の立ち退きが完了すれば、行政は道路の拡張工事を開始します。
道路拡張による立ち退きは拒否できるのか
結論から言うと、道路拡張による立ち退き要請を拒否し続けることは困難です。なぜなら、都市計画法に基づく道路拡張では、最終手段として、行政による土地収用の強制執行が認められているためです。
行政側の一方的な要請により、自身が保有する土地から立ち退かなければならないことを理不尽に感じる方は多いでしょう。しかし、法律で最終的な強制執行が定められている以上、立ち退きを拒否し続けるのは現実的ではありません。
この場合、後の生活のためにも、「いかにして十分な内容の補償を受けるか」を重視すべきでしょう。
立ち退き交渉のポイント
立ち退きを求められた住民が十分な補償を受けるには、立ち退き交渉が重要になります。
うまく交渉を進めるには、次の2つのポイントを重視するようにしましょう。
ポイント1 物件の重要性を主張する
前述のとおり、立ち退き料の一部として支払われる迷惑料は、個々の事情によって金額が大きく異なります。十分な補償を受けるためには、住民は迷惑料の交渉にも力を入れなければなりません。
迷惑料として十分な金額を受け取るために重要なのが、自身にとっての物件・土地の重要性を主張することです。
各々の物件・土地の重要性によって、迷惑料の金額は上下します。物件・土地の重要性が高ければ、それだけ物件・土地を失う住民の不利益は大きいとして、支払われる迷惑料は高くなる可能性が高いです。反対に、住民にとって物件・土地の重要性が低いと判断される場合には、迷惑料の金額は低くなるでしょう。
よって、立ち退き交渉にあたっては、自身にとってのその物件・土地の重要性をしっかり主張する必要があります。
ポイント2 弁護士に交渉を依頼する
立ち退きでは、法律や裁判例を踏まえて交渉を行うことで、より合理的な主張が可能になります。また、うまく交渉を進めるには、交渉の技術も必要でしょう。
そこでおすすめしたいのが、弁護士に代理交渉を依頼することです。不動産問題を得意とする弁護士に依頼すれば、豊富な知識と経験のもと、より住民に有利な内容で交渉を進めてもらうことができます。場合によっては、立ち退き料を増額できる可能性もあるでしょう。
また、立ち退き交渉は住民にとって、体力的にも精神的にも大きな負担となります。これを軽減するためにも、弁護士による交渉代行は有効です。
立ち退き要請を受けた時には、まず弁護士に相談し、交渉や手続きなどに関して力を借りるようにしましょう。
立ち退き料受け取り時の注意点
立ち退き料は、受け取って終わりではありません。立ち退き料の受け取り後には、申告手続きが必要です。
この手続きに際しては、次の2点に注意しましょう。
注意点1 確定申告が必要
立ち退き料は、譲渡所得・事業所得・一時所得のいずれかとして、所得に計上すべきものです。そのため、確定申告の対象となります。
確定申告を行うのは、立ち退き料を受け取った年の翌年です。その年の2月16日~3月15日の間に、住民は税務署に申告書や関連書類を必ず提出しなければなりません。
必要な書類は、通帳の写しや源泉徴収票(会社員の場合)、青色申告決算書(個人事業主の場合)などです。確定申告が可能な期間は限られているので、スムーズに申告手続きを進めるためにも、必要な書類は事前に用意しておくようにしましょう。
注意点2 譲渡所得には特別控除がある
道路拡張により土地や持ち家を失ったなど、保有資産の消滅に対する補償として立ち退き料を受け取った場合には、その立ち退き料は譲渡所得となります。
通常、譲渡所得には税金がかかりますが、立ち退きの場合には「収用特例」という節税制度を利用することが可能です。
この制度では、条件を満たせば、5,000万円の特別控除を受けることができます。つまり、立ち退き料から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が5,000万円以下である場合、税金はかかりません。
立ち退き料の受け取りに際しては、控除制度もうまく利用し、負担を減らすようにしましょう。
まとめ
道路の拡張工事による立ち退きで、住民が受け取れる立ち退き料の金額は、その土地の公示価格や立ち退きによって失う土地の広さ、工作物の有無などによって大きく異なります。
また、住民にとっての物件や建物の重要性によっても、補償額には差が出ます。その重要性が高ければ補償額は高くなり、重要性が低ければ補償額も低くなる可能性が高いです。
交渉をうまく進め、より有利な条件を相手から引き出すためには、住民自らが交渉を担うのではなく、弁護士に代理交渉を依頼することを検討しましょう。
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢