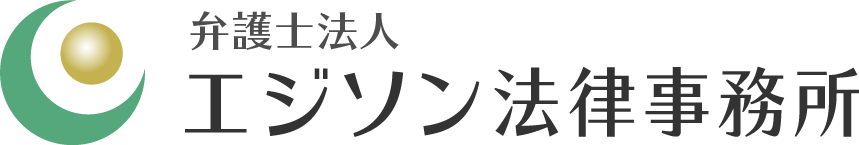コラム
オーナーチェンジ後に店舗からの立ち退きを求められたら

店舗のオーナーチェンジをきっかけに、立ち退きを求められるケースがあります。
多くの場合、新しい貸主から「所有者が代わった」という通知を受け取った直後に「賃貸契約の更新拒絶通知」や「解約予告通知」などが届きます。
経営者の立場からすると、突然のことで戸惑う方も少なくありません。
「本当に出ていく必要はあるのか」「出ていくとすれば、立ち退き料はいくらになるのか」など、疑問に思われる部分もあるでしょう。
今回は、オーナーチェンジによる店舗からの立ち退きにおいて、注意すべきポイントや立ち退き料の目安などについて、わかりやすく解説していきます。
そもそも立ち退きには正当事由が必要
新しいオーナーから立ち退きを求められた場合、「仕方ないか」と考え、立ち退きをすぐに受け入れてしまう方もいるでしょう。しかし、オーナーが変わったからといって、店舗が必ずしも立ち退く必要はありません。
なぜなら法律上、賃貸人が賃借人に立ち退きを求めるためには、「正当事由」が必要であるためです。
土地や建物の賃貸借契約について定める借地借家法第28条によると、立ち退き要求に必要な正当事由の有無は、以下の要素を総合的に勘案して判断されます。
・建物の使用を必要とする事情(貸主・借主それぞれ)
・建物の賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況
・建物の現況
・財産上の給付(立ち退き料)
貸主側の建物使用の必要性が借主よりも極めて高い場合には、正当事由が認められる可能性があります。しかし、貸主側の建物使用の必要性が借主よりも高いとはいえない場合には、正当事由は認められません。
「老朽化」「売却」など、正当事由の具体例については「【賃貸の借主向け】立ち退きの正当事由を弁護士が徹底解説」にて詳しく解説しています。
また、財産上の給付にあたる立ち退き料の支払いにより、貸主の正当事由を補完することができます。立ち退きの正当事由が弱い場合でも、十分な立ち退き料を支払うことで、貸主の正当事由が認められるケースはあります。
正当事由が無ければ拒否しても問題ない
借地借家法第28条を踏まえると、貸主側に正当事由が認められない場合、借主が立ち退き要求に応じる必要はありません。その場合、借主は要求を拒否し、対象の物件に住み続けることができます。
中には立ち退き要求を受けてから10年居座った判例も存在します。
立ち退き要求を受けたときには、まず正当事由の有無について確認したうえで、その後の対応を決める必要があるでしょう。
ただし、正当事由の有無に関する判断は、単純なものではありません。ケースによって状況や判断は大きく異なり、正しい判断を行うには過去の判例を参考にする必要も出てきます。
正当事由について適切に判断を行うためには、立ち退き問題の実績豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
オーナーチェンジ時の立ち退きにおける主な正当事由
オーナーチェンジによる立ち退き要求において、新しいオーナーが主張する主な正当事由としては、以下のようなものが考えられます。
・老朽化による取り壊し・建て替え
・貸主の自己使用
それぞれの主張が正当事由として成立するかの判断について、詳しくみていきましょう。
老朽化による取り壊し・建て替え
立ち退きを求めるオーナー側の主張としてまず考えられるのが、「建物が老朽化しているため取り壊す(建て替える)必要がある」というものです。オーナーチェンジの有無に関係なく、建物の老朽化は確かに正当事由として認められる可能性があります。
ただし、建物の老朽化が正当事由となるのは、老朽化の程度が著しく、使用に危険があるような場合です。ただの老朽化では、正当事由が認められる可能性は低いと考えられます。
また、老朽化を理由に入居者やテナントを退去させた後でその物件を売却するなど、オーナー側に利益を得ようとする意図がある場合には、裁判所による正当事由の判断は厳しくなる傾向にあります。
貸主の自己使用
新しいオーナーが自分で使用することを目的に、既存の入居者やテナントに立ち退き要求を求めることもあります。
しかしこのような貸主の自己使用による立ち退きに、正当事由が認められる可能性は低いです。「貸主が物件を使いたいから」と既存の入居者が追い出されるようなことになれば、借主は大きな不利益を被ることになり、その権利は守られません。
店舗の立ち退き料の目安
他サイトでは「店舗の立ち退き料の相場は家賃の2~3年分」と表現されていますが、これはあくまで目安に過ぎません。
先述のとおり、立ち退き料は正当事由の補完要素となるものです。ケースによって貸主の主張や状況は異なり、立ち退き料によって補完すべき度合いにも違いがあることから、立ち退き料の金額はケースバイケースとなります。
したがって、立ち退き料の目安や相場を具体的に述べることはできません。
参考までにエジソン法律事務所が過去に行った、店舗の立ち退き料増額事例を紹介します。
・賃料18万円の雑居ビル1F(居酒屋)からの立ち退き→最初の提示額400万円から1000万円超へ増額
・賃料30万円の店舗からの立ち退き→1年間のフリーレント+立ち退き料300万円の獲得
(その他の立ち退き事例はこちら)
店舗の立ち退きの場合であれば、退去・移転により生じる借主側の経済的損失の大きさから、住居からの立ち退きに比べ、支払われる立ち退き料は高額になることが多いです。
店舗からの立ち退きの場合、立ち退き料の中で考慮される費用項目には、以下のようなものがあります。
・新店舗への移転・内装工事費用(引越費用、新店舗の契約費、新旧店舗の内装・設備工事費など)
・賃料の差額
・休業・移転に伴う休業補償・営業補償(人件費、固定費、営業損失の補填など)
・借家権価格(認められるケースもあり)
・慰謝料・迷惑料 など
賃料の差額については、数ヶ月分から数年分と、ケースによって補償期間に差が生じます。この点については、立ち退き交渉を通して、なるべく長期に渡っての補償を得ることが重要になります。
また、慰謝料や迷惑料が考慮されることがあり、交渉次第ではこの項目がもっとも高額になるケースも少なくありません。
店舗の立ち退き料の主な考慮要素
店舗からの立ち退きで支払われる代表的な立ち退き料の考慮要素としては、前章で述べたとおり、「移転・内装工事にかかる費用」「賃料の差額」「休業補償・営業補償」などが挙げられます。ここではこれらの項目について、詳しく解説していきます。
①移転・内装工事にかかる費用
立ち退きによって店舗を移転するには、引越費用や新店舗の契約費用がかかります。また、移転先で立ち退き前と同じように店舗を運営するためには、内装工事や設備の設置費用も必要でしょう。
これらの費用は、すべて立ち退きに伴う借主の経済的損失に該当するものであり、立ち退き料による補償対象となります。
住居の場合に比べ、店舗の引越費用や契約費用は高く、業種によるものの内装工事のコストも嵩みます。これらの要素は、店舗の立ち退きで支払われる立ち退き料が高額になる理由の一つです。
②賃料の差額補償
立ち退き前の物件よりも移転先の物件の賃料が高い場合には、その賃料の差額も補償対象になります。例えば、20万円の賃料の物件から30万円の賃料の物件に移転したのであれば、その差額となる「10万円×数ヶ月〜数年分」が、立ち退き料には含まれます。
とはいえ、立ち退き料の金額について合意する前に移転先を決めているケースはまれです。そのため、移転後の具体的な賃料を挙げて、立ち退き料に反映させるのは困難でしょう。
このことから、立ち退き料に賃料差額を反映させる際には、移転先として適当だと考えられるエリアにある、従来と同条件の物件の平均的な賃料をもとにします。また、どれだけの期間の賃料差額が補償されるかは、交渉による部分が大きいでしょう。
これは、住宅からの立ち退きにおける家賃差額の算出でも同様です。
賃料の家賃差額の具体的な計算方法は、「立ち退き料として家賃の差額も請求できる| 算出手順も詳しく解説」にて詳しく解説しています。
③休業補償・営業補償
店舗の移転にあたっては、多くの場合、一定期間の休業が必要になるでしょう。また、移転を原因に営業利益が下がることも考えられます。
これらの点における休業補償や営業補償も、立ち退き料の考慮要素となります。
具体的には、休業中の本来得るはずであった営業利益や人件費、光熱費などの固定費、営業効率悪化による損失などが、立ち退き料の補償対象になります。特に店舗の場合、移転先探しや内装工事、引越などに時間がかかり、移転による利益の変動も受けやすいため、休業補償・営業補償の項目は重要な考慮要素となります。
④得意先の喪失に対する補償
これも営業補償の一種に該当しますが、得意先の喪失に対する補償も、立ち退き料では考慮されます。例えば飲食店などにおいて近隣住民の来店に支えられている場合、移転により一時的に大きく売上が落ちることが予測できます。
このような得意先喪失による収益減も、立ち退き料としてしっかり補償を受けるべき項目の一つです。
競売によるオーナーチェンジでは立ち退き料が出ないのか
一般的な不動産売買によるオーナーチェンジでの立ち退きでは、前述のような考慮要素をもとに、入居者やテナントに対し、立ち退き料が支払われます。
しかし、競売によるオーナーチェンジでの立ち退きの場合、抵当権設定後に賃貸借契約を締結した入居者・テナントに対し、立ち退き料は基本的に支払われません。
なぜなら、新オーナーと入居者・テナントの間に賃貸借契約は締結されていないためです。入居者・テナントは前オーナーに対する引越費用等の請求権を持ちますが、新オーナーに対しての請求権は持ちません。これは、敷金についても同様です。
ただし、抵当権設定前に賃貸借契約を締結していた入居者・テナントについては、競売後も賃貸借契約は新オーナーに引き継がれ、継続となります。この場合の立ち退きでは、立ち退き料も支払われるべきであると考えられます。
立ち退き料の増額は弁護士へ無料相談を
オーナーチェンジによるケースに限らず、賃貸人から立ち退きを要求された場合には、十分な金額の立ち退き料によって補償を受けることが大切です。立ち退き料については、立ち退きにより生じる経済的損失を踏まえ、交渉によって増額を目指すことも検討しましょう。
立ち退き料の増額交渉は、エジソン法律事務所へご依頼ください。増額の成功実績が豊富な弁護士が、代理交渉を行い、より良い条件を引き出します。
立ち退き問題にお悩みの方は、まずは無料相談をご利用ください。
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢