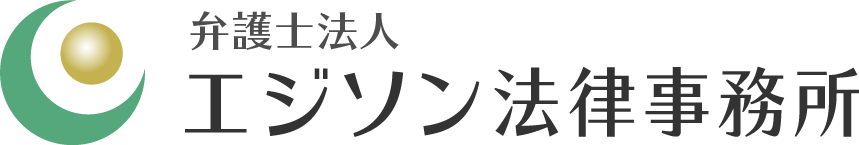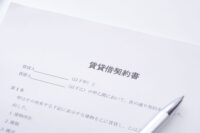コラム
立ち退き料請求の流れ|相談・交渉・和解の進め方

賃貸で住宅や店舗を借りていると、大家から「出ていって欲しい」と言われることがあります。これが、いわゆる「立ち退き」です。
立ち退き要求の理由は、建物の老朽化や大家の自己使用などさまざまですが、法律上、入居者である賃借人が「本当に」出ていかなければならないケースは、多くありません。賃借人は物件から出ていく場合、補償として、十分な金額の立ち退き料を受け取れることもあります。
そこで今回は、大家などから立ち退きを求められた場合に、適切な金額の立ち退き料を請求するための手続きの流れについて、わかりやすく解説していきます。
①弁護士へ相談・依頼
賃貸物件などからの立ち退き要求について、適切な対応を取るには、法的な知見や交渉の技術が必要です。
「本当に立ち退かなければならないのか」「立ち退き料としていくらを提示すればいいのか」など、疑問や不安を抱える方は多いでしょう。
賃借人が、自分で立ち退きに対応することが難しいと感じた場合には、不動産問題を扱う弁護士に相談・依頼することを検討しましょう。
弁護士は、法律や判例にもとづいて、正当事由の有無や立ち退き料の金額を正しく判断するとともに、大家側との代理交渉を行います。
また、もし手続きが裁判に移行した場合でも、賃借人は弁護士にその手続きを任せることができます。
賃借人自身の負担を軽減し、スムーズに手続きを進めるためにも、賃貸人から賃貸借契約の更新拒絶通知を受けたときには、弁護士に相談することを検討してください。
立ち退き料が請求できないケース
大家から立ち退きを求められた場合でも、立ち退き料を請求できないケースがある点には注意が必要です。具体的には、以下のようなケースでは、立ち退き料を請求できない可能性が高いです。
・立ち退きに合意する旨を書面にサインしている
・対象物件からすでに転居している
・賃借人に重大な契約違反がある
・定期借家契約・定期借地契約である
立ち退き料の支払いは、法律で定められたものではありません。スムーズに立ち退きに合意してもらうことを目的に、賃貸人が支払うものです。したがって、すでに立ち退きについて合意している場合や転居を済ませてしまっている場合には、賃貸人が立ち退き料を支払う必要性はなくなってしまいます。
そして長期にわたる家賃滞納や迷惑行為など、賃借人に重大な契約違反がある場合も、立ち退き料は支払われない可能性が高いです。契約違反を理由に、賃貸人は賃貸借契約を強制的に解除することができるためです。
また、定期借家契約・定期借地契約とは、契約期間があらかじめ決められている賃貸借契約のこと。この形で契約を締結している場合、契約期間満了にあたって賃借人は必ず出ていかなければならず、立ち退き料も支払われません。
弁護士費用
弁護士への依頼には、一定の費用が発生します。多くの場合、費用項目は「相談料」「着手金」「成功報酬」「その他手数料・実費」に分けられます。
具体的な金額は、弁護士事務所によって大きく異なり、一概に相場を述べることはできません。料金体系や金額については、事前に確認しておきましょう。
エジソン法律事務所では、以下の料金体系でご依頼を受け付けています。
相談料:初回60分まで0円
成功報酬:「増額幅」に対し35%+税(上限)※
※大家側から金額の提示がない場合には獲得した利益
又は既に提示されている立退料がある場合には、弊所の介入により増加した利益
実際に増額幅が300万円を超える場合には、報酬率が30%+15万円など段階的に下がる仕組みです。
弊所は、初期費用の支払いが困難な方でもご利用いただけるよう、初回相談と着手金が無料です。立ち退き料の回収に成功した場合には、その金額に応じて、成功報酬をお支払いいただきます。
②立ち退き料の調査
次に、立ち退き料の適正金額を把握するための調査を行います。この調査の主なポイントは、以下の2点です。
1.正当事由の該当性
請求できる立ち退き料の金額は、賃貸人が主張する正当事由によって異なります。正当事由の有無は、以下の要素によって判断されます。
・賃貸人・賃借人それぞれが建物の使用を必要とする事情
・建物の賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況
・建物の現況
・財産上の給付(立ち退き料の支払い)
財産上の給付(立ち退き料の支払い)は、1〜4の要素による正当事由を補完する役割を果たすものです。したがって、1〜4の内容によって、支払われるべき立ち退き料の金額は変わります。
これらの要素から立ち退き料を算出するには、過去の判例などを参考にする必要があります。
2.賃借人の経済的損失
立ち退き料の具体的な金額は、立ち退きによって賃借人が被る経済的損失をもとに割り出すこともあります。立ち退きで賃借人が被る経済的損失には、以下のようなものがあります。
・転居費用
・新居の契約費用
・新旧家賃差額
・その他(慰謝料、借地権価格など)
これらの経済的損失は、賃貸人による立ち退き料の支払いで補償されるべきものです。したがって、これらの損失を合算したものを、立ち退き料の根拠にすることがあります。
また、立ち退きを求められたのが住居でなく店舗であれば、営業損失の補填や内装工事費用なども、立ち退き料による補償対象に含まれます。
家賃差額の補償期間や慰謝料の金額については、後の交渉で決めていくことになります。交渉の結果によっては、これらの金額が立ち退き料の最も大きな割合を占めることもあるため、立ち退き交渉の進め方は非常に重要です。
算出方法について、いくつか記事を執筆しておりますので、下記を参考にしてください。
家賃差額の計算方法:立ち退き料として家賃の差額も請求できる| 算出手順も詳しく解説
慰謝料・迷惑料について:立ち退き料に迷惑料は含まれる?内訳や交渉のコツを解説
③交渉
請求する立ち退き料の金額が決まったら、賃貸人との交渉に入ります。立ち退き料の金額について、具体的な根拠を提示しながら、交渉を進めましょう。
退去期限や原状回復義務の有無なども、この時に認識をすり合わせておきましょう。
弁護士に依頼した場合であれば、多くの場合、立ち退き交渉は弁護士が代理で行います。必ずしも、借主が同席する必要はありません。
特に「建物の老朽化+建て替え」を理由とする立ち退きでは、原状回復義務が免除されるケースがあります。(実際に当事務所の交渉では、こうした場合の9割以上において、原状回復義務なしで合意に至っています。)
立ち退きの際の原状回復義務については、下記の記事にて詳しく解説しています。
大家都合により退去する際に原状回復費用は負担する必要があるのか?
裁判をする場合
交渉で双方が合意できなかった場合には、裁判へと手続きを進めることもあります。
早期解決を重視するなら、当事者間の話し合いである「調停」にて和解を図るのも手です。
ただし長い目で見て粘り強く交渉し、場合によっては訴訟を行う方が良い場合もあります。
裁判・調停の具体的な手続きについては、基本的に依頼した弁護士に任せると良いでしょう。
④解決
交渉で合意できた場合には、合意書を作成し、賃貸人・賃借人の双方が署名捺印を行います。署名する前に、「決めたことが反映されているか」「合意していない内容が記載されていないか」など、合意書の内容をよく確認しておくようにしましょう。
また、裁判で和解する場合には、和解調書を作成・締結することになります。この手続きは、双方の代理人弁護士によって行われ、賃借人本人が署名等を行うことはありません。
合意・和解後には、賃借人は明け渡し期日までに物件の明渡を行い、賃貸人からは立ち退き料の支払いが行われます。
裁判でも和解できない場合
裁判で和解できなかった場合には、裁判所の判決を受けることになります。また、この判決に不服がある場合には、控訴による上級審が行われる可能性も考えられます。弁護士のサポートのもと、適切に対応していくことをおすすめします。
エジソン法律事務所の増額実績
エジソン法律事務所では、立ち退き料の増額サポートに力を入れています。
下記にて、具体的な事例を簡単に紹介させていただきます。
賃料10万円のマンション老朽化→立ち退き料200万の増額成功
賃料5万円のアパート老朽化→立ち退き料120万円+3ヶ月分のフリーレントを獲得
賃料7万円のマンション老朽化→当初の提示額60万円から400万円超への増額成功
家賃20万円のマンションから退去請求→300万円超の立ち退き料増額成功
その他の事例に関しては、弊所の立ち退き事例でもご紹介しています。また、弊所のGoogleマップの評価もご覧ください。
立ち退き料の増額は弊所へ相談を
立ち退き料増額のための交渉は、エジソン法律事務所へぜひご依頼ください。立ち退き料の増額に多くの実績を持つ弁護士が、依頼者様に代わって力強く交渉を行います。
また弊所では「弁護士費用のほうが高くついてしまい、損してしまった!」ということがないよう、完全成功報酬制を採用しております。
初回相談料・着手金は0円です。まずはお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから:問い合わせフォーム
記事監修 : 代表弁護士 大達 一賢